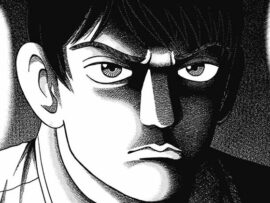2024年8月14日、北海道知床半島にそびえる羅臼岳で、登山に訪れていた26歳の男性がヒグマに襲われ、翌日には遺体で発見されるという痛ましい事故が発生しました。死因は外傷による失血死と判明しており、知床半島における登山客のヒグマ襲撃による死亡事故は今回が初めてのことです。本来、人間を警戒し避けるはずのクマが、なぜ人里に接近し、襲撃する事態が増加しているのでしょうか。本記事では、クマの生態と行動様式を動物生態学の専門家の見解を交えながら深く掘り下げ、人間とクマが安全に共存するための知見と対策について解説します。
知床羅臼岳での悲劇:ヒグマ襲撃事件の背景
今回の痛ましい事故を引き起こしたのは、北海道に広く生息する大型のヒグマです。一方、本州や四国には、ヒグマより小型のツキノワグマが生息しており、それぞれ異なる特徴を持っています。東京農業大学地域環境科学部で動物生態学を研究する山崎晃司教授(「崎」は正しくは「立さき」)に、両者の特徴について詳しくお話を伺いました。
 日本の森林に生息するヒグマまたはツキノワグマの一般的な姿。人里への出没が増加し、適切な距離と対策が求められる。
日本の森林に生息するヒグマまたはツキノワグマの一般的な姿。人里への出没が増加し、適切な距離と対策が求められる。
日本に生息する二種のクマ:ツキノワグマとヒグマの生態学的特徴
小型で植物質食が中心のツキノワグマ
ツキノワグマは世界に生息する8種のクマの中でも小型に分類されます。山崎教授によると、オスの平均体重は約80kgから100kg、メスは40kgから60kg程度です。彼らは食肉目に属するものの、進化の過程で木登りや木の実、葉を食べるようになり、現在の食性の9割以上が植物質で占められています。一般的にイメージされるような肉や魚を食べることは稀だと言います。
大型で動物質にも依存するヒグマ
対するヒグマは、その身体の大きさが際立っています。オスの大型個体では400kgに達し、メスでも平均で100kgを超える個体が存在します。食性に関しては、ツキノワグマと同様に植物質が主な食べ物で約8割を占めますが、シカなどの動物質にやや依存する傾向が見られます。サケを食べるヒグマも知られていますが、現在ではサケが自然に遡上できる河川が減少したため、知床に生息する一部のヒグマに限定されると山崎教授は指摘しています。
クマの活動時期と冬眠・繁殖期の注意点
クマが活発になる時期とその理由を理解することは、人里での遭遇リスクを減らす上で極めて重要です。
活動が活発化する春から夏:食料不足が背景
クマは冬眠を行いますが、これは寒さへの適応というよりも、食料が乏しい時期に体力を温存するための戦略です。通常、3月末から4月上旬にかけて冬眠から目覚めます。春から夏にかけては、冬眠で消耗した体脂肪を回復させるために多くの食料を必要としますが、この時期はまだ山の恵みが少ないため、クマにとっては「耐え忍ぶ時期」とされます。結果として、この期間に食料を求めて人里に出没するケースが増加し、注意が必要です。秋にはドングリなどの実が豊富になりますが、不作の年には、やはり秋にも人里への出没が報告されます。
繁殖期と雄グマの危険な行動「子グマ共食い」
羅臼岳の事故では、親グマだけでなく子グマも目撃されています。NPO法人日本ツキノワグマ研究所の米田一彦理事長によると、ツキノワグマの繁殖期は6月、出産は1月です。繁殖期の雄グマは非常に気が立っており、「共食い」をするほど危険性が増します。自分の遺伝子を残すため、雄グマが母グマが連れている子グマを捕食することがあります。これは、子グマがいる間は母グマが交尾に応じないため、その妨げとなる子グマを取り除くという本能的な行動です。このような時期には特に警戒が必要です。
人間との距離が縮まったクマ:原因と求められる共存の意識
本来人間を恐れるクマが、近年、人慣れし、人を襲うようになった背景には、観光客による餌やりや不用意な接近、写真撮影などが挙げられます。こうした人間の無責任な行動が、クマの行動パターンを変化させ、人間に対する警戒心を薄れさせてしまっているのです。野生動物と人間の境界線が曖昧になることで、予期せぬ遭遇や悲劇的な事故のリスクが高まります。
まとめ:クマとの適切な距離を保ち、安全な共存を目指して
クマは生態系の中で重要な役割を担う野生動物であり、その生息環境が人里と接近する現代において、私たちは彼らとの適切な距離と共存の意識を持つことが不可欠です。本記事で解説したクマの生態、活動時期、そして繁殖期の行動パターンを理解することは、遭遇リスクを最小限に抑える上で役立ちます。具体的には、安易な餌やりは絶対に行わず、ゴミを適切に管理し、山に入る際にはクマ鈴などの対策を講じ、クマの生息域に不用意に立ち入らないことが求められます。私たち一人ひとりが責任ある行動を取ることで、人間もクマも安全に暮らせる社会の実現を目指しましょう。
参考文献
- Yahoo!ニュース (2024年8月27日). クマは本来、肉を食べたり魚を食べたりすることはほとんどない. https://news.yahoo.co.jp/articles/1d26e8ebe5e5bf4e2c7c2dea43c2962a25e613bb