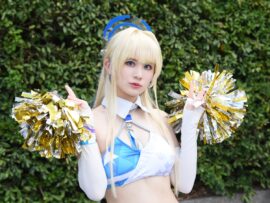転職を通じて理想のキャリアを実現することは、多くの日本人にとって依然として高いハードルとなっています。キャリア形成の専門家である経営学者の石山恒貴氏は、日本企業特有の「いったん枠から離れると戻れなくなる」という雇用構造の問題点を深く理解する必要があると指摘しています。これは、個人のキャリア自律性を妨げ、労働市場の流動性を阻害する要因となっています。
 自身のキャリアパスについて思案するビジネスパーソンのイメージ
自身のキャリアパスについて思案するビジネスパーソンのイメージ
日本的雇用の実態:最新データが示す課題
日本的雇用の負の側面を浮き彫りにするため、リクルートワークス研究所は2024年2月から3月にかけて国際比較調査を実施しました。この調査は、大卒以上の30代、40代の企業雇用者を対象とし、日本、ドイツ、フランス、英国、米国、中国、スウェーデンの計7カ国を比較しています。
リクルートワークス研究所が指摘する日本の雇用に関する主要な課題は以下の4点です。
- 「枠」から外れると戻れないこと: 一度正規雇用のレールを外れると、元の待遇や働き方に戻ることが極めて困難であるという実態。
- 男女間の賃金格差の問題: 性別による賃金の不公平が依然として根深く存在していること。
- 個人における学びと仕事の結びつきに関する認識の希薄さ: キャリア形成における自己投資や学習意欲が諸外国と比較して低い傾向にあること。
- 個人のキャリア自律性が妨げられていること: 企業主導のキャリア形成が優位であり、個人が主体的に自身のキャリアを選択・決定しにくい環境。
これらの課題は、無限定性、標準労働者、マッチョイズムから成る「三位一体の地位規範信仰」と呼ばれる日本独自の雇用慣行と強く関連しています。この信仰が、個人の働き方やキャリア選択に大きな影響を与えていると考えられます。
「枠」から外れると戻れない日本特有の構造
特に深刻なのは、「いったん『枠』から外れると戻れない」という日本特有の構造です。調査では、「今の会社を辞めることになったとしても、希望の仕事につくことができる」という質問に対し、「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」と回答した人の割合が、各国間で大きく異なります。
- 日本: 28.2%
- ドイツ: 77.9%
- フランス: 65.4%
- 英国: 73.3%
- 米国: 68.8%
- 中国: 74.1%
- スウェーデン: 57.9%
このデータから明らかなように、日本のみが3割を下回る低い数値にとどまっており、諸外国が50%から70%台であるのと対照的です。
さらに、「一度働くのをやめてブランク期間を経ても、再び同じような待遇や働き方が選べる」という質問に対しても、同様の傾向が見られます。
- 日本: 23.4%
- ドイツ: 74.6%
- フランス: 65.7%
- 英国: 68.3%
- 米国: 66.2%
- 中国: 67.7%
- スウェーデン: 56.6%
これらの結果は、一度キャリアのレールを外れると、日本においては希望する職種や同等の待遇に戻ることが極めて困難であることを示しています。ここでいう「枠」とは、他でもない「三位一体の地位規範」であり、特に「標準労働者(正社員)として働き続ける」という条件を満たさなければ、個人のキャリア形成において著しく不利になるという日本の現状を端的に表していると言えるでしょう。
結論
リクルートワークス研究所の最新データは、日本の雇用システムが抱える根深い問題を浮き彫りにしました。特に「一度枠から外れると戻れない」という構造は、個人のキャリア選択の自由を大きく制限し、労働市場の柔軟性を阻害しています。人口減少が進む現代において、このような硬直した雇用慣行は、企業にとっても個人にとっても持続可能な成長を妨げる要因となりかねません。今後、より多様な働き方やキャリアパスが尊重されるよう、日本社会全体の雇用システムや人々の意識改革が喫緊の課題と言えるでしょう。