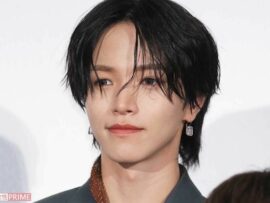立憲民主党は、野田佳彦代表の指導の下、「政権交代の絶好のチャンス!」と意気軒昂に盛り上がりを見せている。しかし、連携が期待される国民民主党や日本維新の会からは同様の熱意が感じられず、既に「終戦ムード」との観測もささやかれ始めているのが現状だ。こうした高揚感に冷や水を浴びせているのが、立憲民主党の安住淳幹事長の不用意な言動である。
長年の人間関係があるとはいえ、安住幹事長が会見の場で国民民主党の玉木雄一郎代表を「玉木」と呼び捨てにするなど、その発言が物議を醸している。この件について玉木代表は「(安住氏は)態度と口が悪いんですよ、いつも」と述べ、野田代表も「行儀が悪いんだよ」と応じたという。昔からの知人たちにとっては「いつものキャラ」という認識なのかもしれない。しかし、両者の関係性を知らない一般国民の目には単に傲慢に映り、「一体何様だ」といった批判記事も少なくない。
安住幹事長の不用意な発言が党に与える波紋
安住淳幹事長の「態度と口の悪さ」が報じられたのは今回が初めてではない。特に、政権交代を目指す最大野党の幹事長という要職にある人物の発言は、党全体のイメージを大きく左右する。国民民主党や日本維新の会との連携が不可欠な状況で、主要なパートナーである玉木代表への敬意を欠く態度は、協力体制の構築に深刻な影響を及ぼしかねない。
政治における言葉遣いや態度は、有権者へのメッセージとして非常に重要だ。親しい間柄での「呼び捨て」が許されるとしても、公の場でそれを貫くことは、国民に対する配慮の欠如と受け取られるリスクがある。これは、単なる個人の癖という範疇を超え、政治家としての資質、ひいては所属政党の姿勢までもが問われる問題となる。
 立憲民主党の安住淳幹事長が会見で発言する様子。その言動が政治的波紋を呼んでいる
立憲民主党の安住淳幹事長が会見で発言する様子。その言動が政治的波紋を呼んでいる
過去にも物議を醸した「安住流」メディア対応
安住幹事長の言動が批判の対象となったのは、前述の玉木代表への呼び捨てに留まらない。約5年前、彼が国会対策委員長を務めていた際には、マスコミ相手にその「能力」を発揮し、不興を買った過去がある。特に顕著だったのが、2020年2月に報じられた通称「壁新聞」騒動だ。(以下、「週刊新潮」2020年2月20日号掲載記事を基に再構成。肩書は当時)
国会内にある立憲民主党の控室の扉に、2020年2月4日付の朝刊記事6社分が貼り出され、安住氏による「評定」が手書きで書き加えられた。この異例の「壁新聞」は、国会を往来する多くの議員や記者の注目を集めた。
「壁新聞」騒動:メディア評価と政治的思惑の交錯
安住氏の「壁新聞」に記された各紙への評価は以下の通りである。
- 日本経済新聞: 「0点 くず 出入り禁止」
- 産経新聞: 「論外」
- 読売新聞: 「ギリギリセーフ」
- 朝日新聞、毎日新聞、東京新聞: 「花丸(手書きの印で)」「すばらしい!」(特に東京新聞は担当記者の顔写真まで丸で囲まれた)
これらの評価は、前日の衆院予算委員会における与野党の質疑の報道内容に基づくものだった。酷評された日経新聞は、野党側が「『桜を見る会』などの追及ばかりを続けている」という批判をかわしたい思惑があると報じ、産経新聞も立憲民主党幹部のコメントとして同様の地元からの声が上がっていると伝えた。
当時、立憲民主党は1月からの通常国会で「桜を見る会」を政権批判の主要な論点としていたが、折しも新型コロナウイルスの感染者が急増。形勢が不利と判断したのか、2月からは肺炎対策に関する質問に時間を割くよう方針転換していた。酷評された2紙は、こうした政治的な背景や野党への批判を解説したに過ぎない。にもかかわらず、安住氏の逆鱗に触れたのは、党の方針転換や戦略を批判的に報じられたことへの不満が背景にあったと見られる。
一方、同様の指摘をしつつも、立憲民主党の辻元清美議員の質問を「辻元節 鋭く」と評した読売新聞は「ギリギリセーフ」の評価を得た。そして、立憲民主党に比較的紙面を割き、リベラルな論調で知られる朝日新聞、毎日新聞、東京新聞は「花丸」という最高評価を受けたのである。
ある全国紙の政治部デスクは、「どの党の質問を取り上げるかは各社の裁量であり、政治家が口を挟めば表現の自由への圧力と受け取られかねない」と指摘している。これは、メディアが政治権力から独立し、多角的な視点から報道を行うことの重要性を示す事例と言えるだろう。
元NHK記者としての「報じる側」への影響力
安住淳氏は当選8回を数え、野田政権時代には財務大臣を務めるなど、ベテランの政治家である。さらに、彼の経歴において特筆すべきは、NHK政治部記者から政治家に転身したという点だ。報じる側の苦労や論理を熟知しているからこそ、その言動がマスコミに対して与える影響は大きい。
メディアの報道姿勢を公然と「採点」し、特定の新聞社を「出入り禁止」とまで言い放つ行為は、表現の自由に対する間接的な圧力となり得る。自身がかつてメディアの一員であった経験があるからこそ、その発言の重みと影響力を理解しているはずであり、今回の「壁新聞」騒動は、その知識が悪しき方向に作用したと批判されても仕方がないだろう。
結論:リーダーの言動が問われる時代
安住淳幹事長の今回の言動、そして過去のメディア対応は、立憲民主党が目指す「政権交代」への道のりに少なからず影を落としている。党の顔とも言える幹事長が、連携先であるはずの他党の代表を軽んじるかのような発言をしたり、メディアに対し圧力をかけたりする行為は、国民からの信頼を得る上で大きな障壁となる。
現代の政治においては、政策論争だけでなく、政治家一人ひとりの倫理観やコミュニケーション能力が厳しく問われる。特に、支持率が伸び悩み、多様な勢力との連携が求められる立憲民主党にとって、幹事長の言動は党の印象を左右する重要な要素だ。たとえ「いつものキャラ」であったとしても、公の場での発言や態度は常に慎重であるべきだ。政権交代という大きな目標を達成するためには、国民の共感を得られる、より成熟したリーダーシップが不可欠となるだろう。
参考文献
- 『週刊新潮』2020年2月20日号 (掲載記事を基に再構成)
- Yahoo!ニュース「安住淳幹事長」関連記事 (2024年10月19日付)