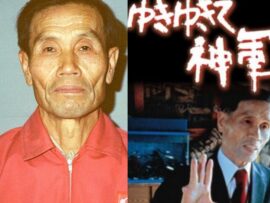人類の歴史は、地球規模の支配を築き上げた壮大な成功の物語として語られることが多い。しかし、その輝かしい繁栄の陰で、ホモ・サピエンスは長らく「借りものの時間」を生きてきたという警鐘が鳴らされている。数千年にわたる栄光の時代は、今や終焉を迎えつつあるのだろうか。この根源的な問いに、ケンブリッジ大学の古生物学・進化生物学専門家であるヘンリー・ジー氏は、最新刊『ホモ・サピエンス30万年、栄光と破滅の物語 人類帝国衰亡史』で深く切り込んでいる。本書は、人類の繁栄の歴史を振り返りながら、我々が直面する絶滅の可能性、その理由、そして避けられない運命から逃れるための希望についても語り、サイエンス作家の竹内薫氏をはじめ、各界の第一人者から絶賛されている。本稿では、作家の橘玲氏による本書の魅力の解説を通じて、地球と人類の未来について考察する。
科学的視点で描く人類の未来:ヘンリー・ジーの洞察
ヘンリー・ジー氏は、ケンブリッジ大学で博士号を取得した古生物学と進化生物学の専門家であり、研究者としてだけでなく、科学雑誌『ネイチャー』のエディターや科学番組の制作に携わってきた。その専門知識を活かした彼の活動は多岐にわたる。前作『超圧縮 地球生物全史』(原題:”A (Very) Short History of Life on Earth”)は王立協会科学図書賞を受賞し、サイエンスライターとしての評価を確立した。およそ46億年前に地球が誕生し、38億年前に生命が生まれた遠大な歴史から、ホモ・サピエンスの未来までをわずか300ページで「超圧縮」して描いた前作は、その卓抜な邦題も相まって大きな話題を呼んだ。
今回の『人類帝国衰亡史』(原題:”The Decline and Fall of the Human Empire”)は、その続編にあたる。前作の最終章で未来の歴史にわずかに触れられていたホモ・サピエンスの絶滅というテーマを、さらに深く掘り下げた内容となっている。ジー氏は、人類がいかにして現在の地位を築き、そしてその支配がいかに脆いものであるかを、客観的な科学的視点から冷静に分析している。
地球の歴史に刻まれた大絶滅:恐竜から微生物まで
生命は、その長大な歴史の中で何度も大規模な絶滅を経験してきた。最もよく知られているのは、約6600万年前の恐竜の絶滅だろう。この謎については、かつて様々な説が唱えられた。個人的に最も興味深いのは、「1億6000万年もの間、地球の支配者として君臨し続けた恐竜は、もはや征服すべき新天地もなくなり、退屈しすぎて死んでしまった」という「古代世界倦怠症」説だ。これはジョークではなく、れっきとした専門用語として存在するというから驚きである。しかし、現在では、巨大な隕石の衝突が恐竜絶滅の主要因であるという説が広く受け入れられている。
あまり知られていないが、生命史上最大の絶滅は約25億年前に発生した「大酸化イベント」によって引き起こされた。当時、陸地はほとんどなく、海は誕生したばかりの生命で覆われていた。これらの生命は最古のバクテリアの一種であるシアノバクテリアで、太陽光のエネルギーを利用して光合成を行い、二酸化炭素と水から有機物を生成していた。この過程で、副産物として遊離酸素が放出された。酸素は、触れたものを酸化させ変質させる性質を持つ「宇宙でもっとも危険な物質の一つ」である。遊離酸素のない海や大気の中で進化してきた当時の生命にとって、これは致命的な環境激変を意味した。地球上の海を覆い尽くしたシアノバクテリアは、自らが作り出した毒物によって絶滅寸前に追い込まれたのだ。この死屍累々の環境の中から、今や大気中に豊富に存在する酸素を取り込んでエネルギーを生成し、二酸化炭素を排出する新たな生命が誕生したのである。
 人類の未来と地球の運命を示唆する、手の上に載せられた地球儀のイメージ画像
人類の未来と地球の運命を示唆する、手の上に載せられた地球儀のイメージ画像
ホモ・サピエンス絶滅の予兆:橘玲が語る「種の老衰」説
地質学の記録から数々の絶滅を観察してきた古生物学者にとって、人類(ホモ・サピエンス)の絶滅もまた、そんなエピソードの一つに過ぎないのかもしれない。一時的に繁栄した者たちもいずれは滅びるという『平家物語』のような世界観は、かつて「種の老衰(種族衰退説)」として学会の主流を占めていた。しかし、恐竜の絶滅原因が倦怠感ではなく隕石衝突であると明らかになると、こうした直線的な進化の考え方は廃れていった。
ところが近年になり、一部の古生物学者がこの「種の老衰」説を再び提唱し始めたという。それによると、ある種が生態系の頂点に達し、あらゆる競争相手を排除してしまうと、「決してあきらめることのない冷酷な相手」との長い戦いが始まり、最終的には敗北することが運命づけられている。その「敵」とは他でもない「地球そのもの」である。光合成を行う最古の生命であるシアノバクテリアが大酸化イベントで大量絶滅したように、人類もまた、自らが築き上げた文明の重さによってやがて滅び去るのだと、ジー氏は示唆している。この説は、人類が繁栄を享受するほど、その滅亡への道もまた刻々と進んでいるという、根源的な問いを投げかける。
多様性の喪失と人類の脆弱性
ジー氏によれば、人類の運命は5万年前にアフリカを出てユーラシアやオセアニアへと拡散していったときに、すでに決定づけられていたという。この「出アフリカ」の時期に、マンモスのような大型動物だけでなく、中型犬より大きな動物のほとんどが絶滅した。それと同時に、ユーラシア大陸で暮らしていたネアンデルタール人(ヨーロッパ、中央アジア、北アジア)、デニソワ人(アジア中央から東部、チベット高原)、さらには古い種であるホモ・エレクトス(フィリピンのホモ・ルゾネシスや、フローレス島のホモ・フロシエンシス、通称「ホビット」)といった近縁種もみな絶滅に追い込まれた。
ジー氏は「ジェノサイド」という言葉を慎重に避けているが、この大量死に我々の祖先が関与していたことは疑いようがない。競争相手をすべて滅ぼしてしまったことで、人類は種としての多様性を失ってしまったのだ。古代DNAの解析によれば、そもそも人類は、およそ93万年前から10万年以上にわたって絶滅寸前の状態にあり、「地球上すべての繁殖可能な人類を合わせても、その数は常に1280人を超えることがなかった」とされる。多様性が失われると、種は停滞し、外部からの環境変化(地球温暖化など)や、内部からの要因(不妊や少子化といった人口問題)に対して脆弱になる。ローマ帝国が最も輝かしい時代にすでに滅亡の影が差していたように、繁栄の頂点にある人類もまた、この避けられない衰退の運命から逃れることはできないのかもしれない。
絶望の中に灯る希望の光
ヘンリー・ジー氏は、人類がなぜ絶滅へと向かうのか、その理由を淡々と語っていく。しかし、本書は暗澹たる絶望の書ではない。彼が提唱する様々な科学的知見と歴史的証拠は、我々が直面する現実の厳しさを突きつける一方で、最後の章では、この残酷な運命から逃れるための「希望」が明確に提示されている。
我々ホモ・サピエンスが、自らの未来をどのように選択し、いかにしてこの地球という生命共同体の中で持続可能な存在であり続けるか。その答えは、ぜひ本書を手に取り、自らの目で確かめてほしい。人類が直面する最大級の問いに対し、科学的根拠に基づいた洞察と、未来へのポジティブなメッセージは、現代社会を生きる我々にとって深く考えさせられるものとなるだろう。
著者紹介
橘 玲(たちばな・あきら) 作家。2002年に金融小説『マネーロンダリング』(幻冬舎文庫)でデビュー。著書に『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』(幻冬舎)、『日本の国家破産に備える資産防衛マニュアル』『橘玲の中国私論』(以上ダイヤモンド社)、『「言ってはいけない? –残酷すぎる真実』(新潮新書)など多数。最新刊は『シンプルで合理的な人生設計』(ダイヤモンド社)。メルマガ『世の中の仕組みと人生のデザイン』配信など、精力的に活動の場を広げている。(本原稿は、ヘンリー・ジー著『ホモ・サピエンス30万年、栄光と破滅の物語 人類帝国衰亡史』〈竹内薫訳〉に関連した書き下ろしです)