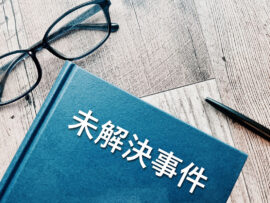2025年12月19日、読売新聞代表取締役主筆・渡邉恒雄氏が死去しました。社報では「戦後最大のジャーナリスト」と称賛されましたが、その死に際し、読売巨人軍元球団代表の清武英利氏をはじめ、親交のあった人々からは「最後の独裁者」と呼ばれた渡邉氏の多面的な実像が語られています。紙面私物化や政治家との癒着で批判も多かった渡邉氏。果たして彼の功績と課題は何だったのでしょうか。
社報の「戦後最大のジャーナリスト」にOBが抱いた違和感
渡邉恒雄氏の訃報は、読売新聞社報の特別号で伝えられました。一面を使い、黒地に白抜きの太い見出しで「渡辺主筆死去」と報じられ、冒頭には「長年、第一線で新聞界を牽引しつつ、自らを『終生一記者』と任じた『戦後最大のジャーナリスト』が人生の幕を閉じた」と記されていました。しかし、この表現に対し、元球団代表で「読売社友」を解かれた清武氏や読売OBからは、複雑な思いや違和感が寄せられたといいます。あるOBは、「自らを『終生一記者』と任じた、という表現は、本人の言葉だからまあいいとしても、その後の『戦後最大のジャーナリスト』が人生の幕を閉じた、には苦笑せざるをえませんでした。はやりの言葉を使えば、盛りすぎじゃないですかね」とメールで語っています。
 読売新聞主筆、渡邉恒雄氏の肖像写真
読売新聞主筆、渡邉恒雄氏の肖像写真
「独裁者」渡邉恒雄氏の多面的な評価とメディアへの影響
人間はプリズムのように多面体であり、一人の人間の中に傲慢さから慈愛まで、多様な人格が同居することがあります。渡邉氏もまた、「オレは最後の独裁者だ」と公言する一方で、多くの人から異なる評価を受けていました。清武氏は、渡邉氏の死後、読売大阪本社社長だった中村仁氏の個人ブログや東大名誉教授・御厨貴氏の厳しい評価を読み、「戦後最大のジャーナリスト」という社報の表現に、OBと同様の違和感を抱いたと述べています。
特に、中村氏のブログ「新聞記者OBが書くニュース物語」は、渡邉氏の「終生一記者」という言葉に触れ、「盟友でもあった中曽根元首相は、将来、使って欲しいという思いで、『終生一記者を貫く 渡辺恒雄の碑 中曽根康弘』の墓碑を贈っています。『終生一記者』というには、ナベツネさんの正確な表現ではない。『一記者』を相当はみ出した異形の記者でした」と指摘しました。経済部出身の論客である中村氏は、渡邉氏の傍で読売を支えた一人であり、彼の言葉は重みがあります。元首脳の一人である中村氏は、30年にわたる渡邉氏の「メディア独裁」が現代のジャーナリズムに与えた弊害を訴え、渡邉氏が戦後の混乱期が生んだ人物であり、現代の政治記者は異なる生き方を模索すべきだと提言しています。
デジタル時代に取り残された「活字文化の守護者」
中村氏の文章は、多くの新聞やテレビが渡邉氏の偉大さを無批判に称えて見送る中で、一つの重要な疑問を投げかけています。それは、パソコンやスマートフォンを毛嫌いし、デジタル化に遅れをとった渡邉氏が、紙媒体の深刻な危機に気づくのが遅れたのではないかという点です。活字文化の守護者を自負しながらも、デジタル化の波に乗り遅れたメディアのドンとして、渡邉氏がこの危機に対し具体的にどのような手を打ってきたのか、という疑問がブログの文章から透けて見えます。清武氏も、主筆室にノートパソコンを持ち込み、巨人軍が開発したベースボール・オペレーション・システムの説明をした際のことを思い出し、渡邉氏がデジタル時代にいかに向き合っていたかを振り返っています。
渡邉恒雄氏の死去は、彼が生涯を捧げた読売新聞、ひいては日本社会におけるメディアのあり方、そして移り変わる情報化社会におけるジャーナリズムの役割について、改めて深く考察する機会を与えています。彼の「独裁者」としての功罪は、今後も議論され続けることでしょう。