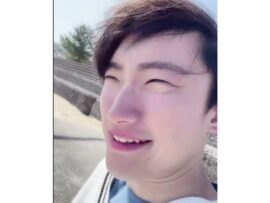近年、日中関係の緊張が高まる中、日本のマスコミが報じる「台湾有事」を巡る世論調査が、ネット上で激しい批判に晒されています。特に、集団的自衛権の行使に関する報道は、「戦争を煽るものだ」として多くの疑問を投げかけられています。一体なぜ、マスコミは日中関係の緊張をさらに高めるかのような「勇ましい」報道を繰り返すのでしょうか?その背景には、戦前の歴史をも想起させる、メディア業界にとっての「禁断の果実」とも呼べる衝撃的な構造が存在すると指摘されています。本稿では、大衆を熱狂させ、時に国を誤った方向へ導きかねない報道の裏にある深層を紐解きます。
「集団的自衛権行使に賛成48%」報道への批判の嵐
2025年11月16日、共同通信が「速報」として配信した「台湾有事での集団的自衛権行使に賛成48%」というニュースは、瞬く間にネット上で大きな反響を呼びました。同社の世論調査で、台湾有事の際に集団的自衛権を行使することの是非を問うた結果、「賛成」と「どちらかと言えば賛成」を合わせた回答が48.8%に達し、「反対」の44.2%を上回ったと報じられたのです。
この報道に対し、ネットユーザーやSNSからは「そんな単純な問題ではない」「質問が雑すぎる」「集団的自衛権を行使したらどうなるか深く考えずに答えている人もいるだろう」といった批判が殺到しました。多くの人々が、このような報道が日中関係をさらに悪化させ、無用な緊張を生み出すのではないかという懸念を表明しています。マスコミは「国民に世論の動向を伝えただけ」という立場を取りますが、その「建前」の裏には、彼ら自身も気づかない深い事情があると考えられます。
 高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁によって日中関係は悪化している
高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁によって日中関係は悪化している
マスコミが「勇ましい報道」を繰り返す深層
なぜマスコミは、国民の反発を招きかねない「勇ましい報道」を繰り返すのでしょうか。この問いを考える上で、メディア業界に潜む「禁断の果実」という概念が浮上します。それは、特定の報道姿勢が大衆の感情を刺激し、一時的な注目や熱狂を生み出すことで、メディアにとっての利益となる構造を指します。過去の歴史、特に戦前の日本においても、大衆を熱狂させ、国を誤った方向へと導いた報道の事例は少なくありません。
現代のマスコミが、台湾有事のようなデリケートな国際情勢において、安易に世論調査の結果を強調し、特定の方向へと世論を誘導するような印象を与えるのは、この「禁断の果実」の誘惑に囚われているからかもしれません。単なる事実の報道というよりも、緊張感を高める見出しや扇動的な表現を用いることで、記事へのアクセス数や視聴率を稼ぎ、結果として広告収入や影響力を維持しようとする無意識的なメカニズムが働いている可能性も指摘されています。
結論
日本のマスコミによる「台湾有事」に関する世論調査報道は、その単純化された内容と、それが引き起こす日中関係のさらなる緊張への懸念から、多くの批判に直面しています。メディアが単に「世論を伝えているだけ」という建前を唱える一方で、その報道の裏には、大衆の熱狂を呼び起こし、メディア自身の利益に繋がるという「禁断の果実」の構造が潜んでいる可能性があります。私たちは、このような報道に接する際、その背景にある意図や潜在的な影響を深く考察し、多角的な情報源から判断する姿勢がこれまで以上に求められています。
参考文献:
- 窪田順生. 「台湾有事で集団的自衛権行使に賛成48%」報道に批判殺到! なぜマスコミは“勇ましい報道”を繰り返すのか? (2025年11月22日). https://news.yahoo.co.jp/articles/b04f8246ede9d4732d67eb58776828495d07ca71