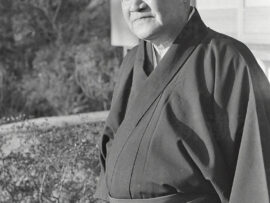警察庁の統計によると、2024年の1年間に自ら命を絶った小中高生の数は529人にのぼり、これは2022年から3年連続で500人を超え、職業別自殺者統計開始以来過去最多の記録となりました。児童青年期の自殺には、家族や家庭環境、友人関係、学校など、様々な社会的な状況が深く影響すると指摘されています。このような子供を取り巻く社会課題を解決するため、政府は2023年4月に「こども家庭庁」(以下、こども庁)を設立し、庁内には専門部署として「子どもの自殺対策室」を新設しました。しかし、そのこども庁には、児童虐待に関する相談が年々増加傾向にあるという報告があります。警察庁の自殺統計でも、19歳までの自殺要因は、学校問題や健康問題に続き、家庭問題が常に上位を占めています。これは、子供たちが置かれている環境がますます厳しさを増している現状を示唆していると言えるでしょう。長年、若者の生きづらさをテーマに取材を重ね、「日本自殺予防学会メディア表現支援委員会」委員も務める渋井哲也氏の著書『子どもの自殺はなぜ増え続けているのか』(集英社新書)から、児童虐待問題の現実について一部を抜粋してご紹介します。(全2回の第1回)
 新宿・歌舞伎町、「トー横」に集う若者たち。深刻な社会課題に直面する世代の一側面。
新宿・歌舞伎町、「トー横」に集う若者たち。深刻な社会課題に直面する世代の一側面。
こども家庭庁に移管された児童虐待対策と相談件数の増加
こども庁は、主に厚生労働省の子供家庭局の業務を引き継ぐ形で設立されました。そのため、児童虐待防止対策に関する業務も2023年4月からはこども庁が担当しています。こども庁は、2025年3月に2023年度の全国の児童相談所(児相)における児童虐待相談対応件数の統計を発表しました。この統計によると、2023年度の相談対応件数は22万5509件に達し、これは前年度と比較して1万666件、率にして5.0%の増加となりました。相談対応件数が増加している背景には、虐待の疑いに対する社会全体の認識が高まり、通報や相談が増えている側面があると考えられます。一方で、相談件数の増加は、少なくとも虐待を受けている子供たちが児相に繋がり、支援を受ける機会が増えていることを意味しており、フォロー体制がある程度機能しているとも言えます。
深刻化する虐待の内訳:心理的虐待が最多
2023年度の児童虐待相談の内訳を見ると、「心理的虐待」が最も多く、全体の59.8%にあたる13万4948件を占めました。これは前年比で6834件、5.3%の増加です。「心理的虐待」に含まれる行為の定義は時代とともに変化する可能性がありますが、増加傾向が続いていることは明らかです。次に多かったのは「身体的虐待」で、5万1623件(22.9%)となり、前年比2159件、4.4%の増加でした。「ネグレクト(育児放棄)」は3万6465件(16.2%)で、前年比1593件、4.6%増加しています。また、「性的虐待」も増加しており、2473件(1.1%)で前年比80件、3.3%の増加となりました。これらの統計は、児童虐待が依然として深刻な社会問題であり、様々な形態の虐待が増加している現状を浮き彫りにしています。
虐待死も高水準を維持:0歳児の死亡が顕著に
児童虐待に関連して子供が死亡に至る「虐待死」の事例も、依然として高水準で推移しています。2024年9月時点で自治体の調査により表面化した児童虐待による死亡事例は65例(子供72人)となりました。このうち、無理心中以外の虐待死は54例(子供56人)、「心中」による虐待死(親は生存したが子供が死亡した未遂を含む)は11例(子供16人)でした。死亡事例を詳細に分析すると、亡くなった子供の年齢は「0歳」が最も多く、25人で全体の44.6%を占めています。さらに0歳児のうち、生後間もない「月齢0カ月児」が15人で60%を占めるという非常に痛ましい現状があります。「3歳未満」まで広げると39人で69.6%にもなり、幼ければ幼いほど虐待死のリスクが高いことがわかります。この「0歳児」に死亡事例が多い傾向は、過去20年間ほとんど変わっていません。ちなみに、死亡事例の中に「自死」は1人(1.8%)含まれていますが、この項目は前回報告からの追加であり、第5次報告以降で初めての「自死」事例として記録されています。
まとめ
近年の統計は、日本の子供たちが直面する「自殺」と「児童虐待」という二つの深刻な問題が、過去最多水準で進行している現実を示しています。特に児童虐待においては、相談件数の増加に加え、痛ましい「虐待死」も依然として高水準にあり、中でも幼い命が犠牲となるケースが後を絶ちません。こども家庭庁が中心となり対策が進められていますが、統計が示す数字は、子供を取り巻く環境の厳しさを改めて浮き彫りにしており、更なる社会全体の取り組みが急務であることを訴えかけています。