迫る参議院選挙の最大の争点である「給付か減税か」。国際政治アナリストの渡瀬裕哉氏は、減税が実現しない最大の要因は「予算編成スケジュールにある」と指摘します。国民が減税を強く望んでも一向に進まない背景を解説します。
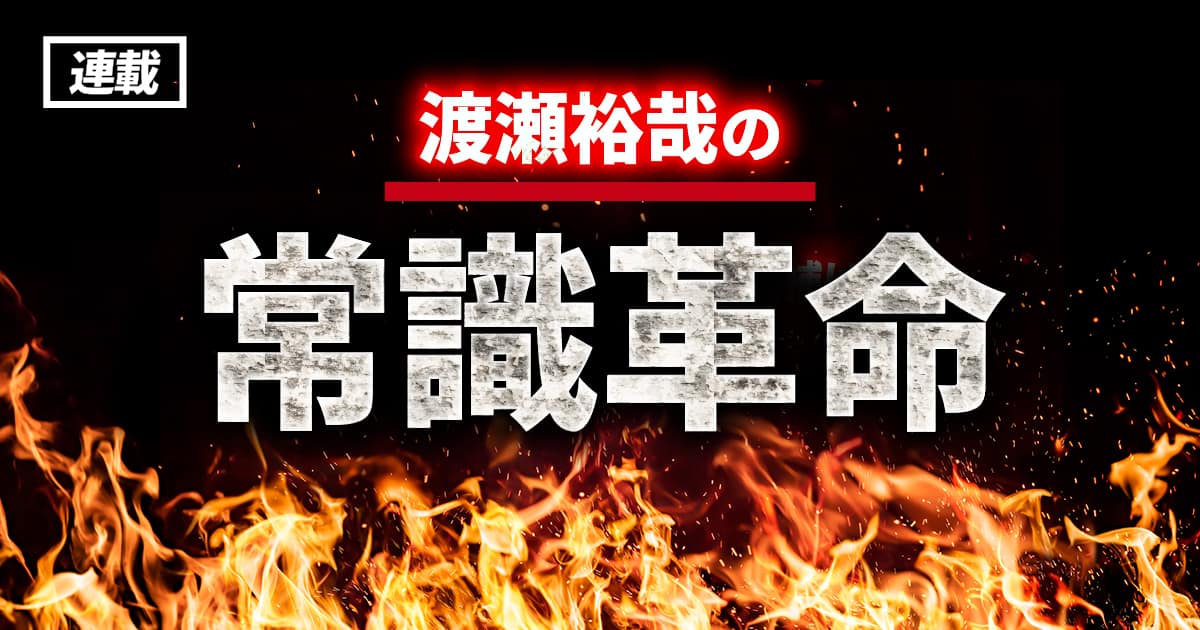 国際政治アナリスト渡瀬裕哉氏の写真と連載タイトル「渡瀬裕哉の常識革命」
国際政治アナリスト渡瀬裕哉氏の写真と連載タイトル「渡瀬裕哉の常識革命」
政権交代しても減税は難しい理由
渡瀬氏によると、減税は一過性の給付よりも恒久的な経済刺激策として遥かに優れています。個人の経済活動を活発化させる効果も明らかです。しかし、現在の日本の政治仕組みには、迅速な減税実行を妨げる致命的な問題があります。これは与党・野党問わず共通の問題であり、仮に政権交代が起きたとしても、この問題がすぐに解決されるわけではありません。
予算編成スケジュールが減税を阻むメカニズム
政治の本質は「スケジュール」であり、その中でも最重要となるのが予算編成です。皮肉にも、この予算編成スケジュールこそが、国民が期待する減税を最も阻害する要因となっています。
具体的な予算編成のスケジュールを見てみましょう。毎年6月には「骨太の方針」が策定され、8月末に各省庁からの「概算要求」が出揃います。その後、9月から12月にかけて「予算査定」が行われ、12月中旬には与党の「税制調査会答申」がまとめられます。これを受けて1月から2月に「税制改正法案」が国会に提出され、3月に「予算成立」となります。国会議員や政府の役人は、この年間スケジュールを前提に行動しています。
議論の余地をなくす「12月決定」
この厳格なスケジュールに従うと、来年度予算の大枠、特に歳入歳出に関する主要な項目は、12月上旬までにはほぼ固まってしまいます。そのため、12月中旬に行われる与党税調の議論では、抜本的な税制改正について深く議論する時間や機会が限られてしまいます。結果として、各省庁や業界団体などの既存の利害関係を調整することが中心となり、「〇〇税の税率を下げるなら、代わりに〇〇税の税率を上げなくてはならない」といった、いわゆる「税収中立」の考え方から抜け出せなくなります。
歳入歳出に関する大きな枠組みが既に決定している中で税制論議が行われるため、根本的な税制改革は進みにくい構造になっています。これにより、日本では大きな改革ではなく、サラミスライス方式と呼ばれるような、少しずつ税負担を増やす「場当たり的な増税」が繰り返されてしまうのです。
結論として、日本の税制において減税が国民の期待ほど迅速に進まない背景には、年間を通じた予算編成の厳格なスケジュールが大きく影響しています。この構造がある限り、抜本的な減税実現には、システムそのものの見直しが必要となる可能性が高いと言えるでしょう。






