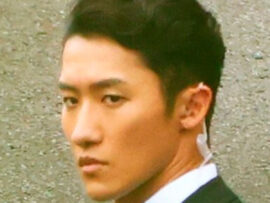世界情勢が緊迫化し、核兵器使用のリスクが現実味を帯びる中、日本はどのような状況に直面するのだろうか。長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)が実施した画期的なシミュレーションは、従来の想定をはるかに超える被害の可能性と、日本の安全保障における「核の傘」の新たな側面を浮き彫りにしている。これはまさに「いま、この世界で核兵器が使用された場合」の具体的な影響を、特に北東アジアに焦点を当てて詳細に分析した初の試みであり、日本における核兵器使用シミュレーションの結果として重い意味を持つ。
長崎大学RECNAは2023年3月、北東アジアでの核兵器使用を想定した複数のケースにおける被害シミュレーションを発表した。米韓のシンクタンクと協力して行われたこのプロジェクトは、「テロリストによる核使用」「ウクライナ侵攻」「台湾有事」など、様々なシナリオを検証した。その結果、明らかになったのは、核がひとたび使用された場合の甚大な被害規模と、日本が攻撃の直接的な標的となるリスクの高さである。
最も多くの犠牲者が出ると予測されたのは、「台湾有事」を想定したシナリオだ。台湾独立に端を発した中国の軍事侵攻に対し、米国が大規模な部隊を投入して交戦状態となった場合、劣勢に立たされた中国がグアム、長崎県の佐世保、沖縄県の嘉手納にある米軍基地を核攻撃するという展開が描かれた。これに対し米国も核で応戦し、米中合わせて24発の核兵器が使用され、わずか数カ月で260万人もの死者が出ると推計された。また、「テロリストによる核使用」シナリオでは、東京で広島や長崎に投下されたものより小型の核が1発使用されただけで、人口や建造物が密集した地域特性から22万人もの犠牲者が出ると見込まれている。
RECNAのプロジェクトメンバーである長崎大学客員教授の鈴木達治郎氏(平和・軍縮問題NPO法人ピースデポ代表)は、シミュレーションの結果を踏まえ、「核兵器が使われた場合、『核の傘』に守られている国こそが、相手国からの核攻撃の標的になり得る」と強く警告している。
日本の安全保障政策において中心的な役割を担う「核の傘」とは、核兵器を持つ米国が同盟国である日本への攻撃を、米国自身への攻撃とみなして核を含むあらゆる手段で反撃すると約束することで、敵国の攻撃を思いとどまらせる「抑止力」として機能させる仕組みである。しかし、このシミュレーション結果は、その「核の傘」が機能しない、あるいは機能しようとした場合に、その「傘」の下にいる国そのものが核の攻撃目標となり、壊滅的な被害を受ける可能性を示唆している。
今回の長崎大学RECNAによる核兵器使用シミュレーションは、「核の傘」という安全保障の考え方に対して、改めてその現実的なリスクと脆弱性を突きつけるものとなった。日本が国際社会の核リスクと無縁ではいられない現状において、シミュレーションが示した被害の大きさや、同盟関係に基づく安全保障の代償について、深く議論し、新たな安全保障のあり方を模索する必要性が高まっている。
 長崎大学の鈴木達治郎氏。核兵器使用シミュレーションの結果に基づき、「核の傘」が標的になる現実について語る。
長崎大学の鈴木達治郎氏。核兵器使用シミュレーションの結果に基づき、「核の傘」が標的になる現実について語る。