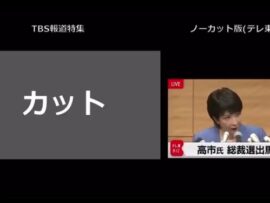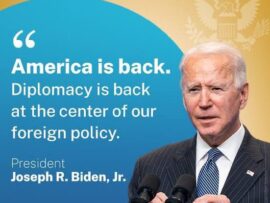ヤクザの抗争に巻き込まれ、一人娘を失った母親、堀江ひとみさんは、「ヤクザ撲滅」を誓い、暴力団組長に対する民事訴訟を起こした。我が子を無惨に殺された親の戦いは、予想もしない困難と危険に満ちていた。民事裁判が始まると、ひとみさんは連日、身の危険に晒されることになる。この異例の民事訴訟は、日本の社会問題としての暴力団の存在、そして被害者遺族が直面する司法と現実の壁を浮き彫りにした。
裁判と並行する脅迫行為、そして警察の警護
民事裁判の開始とともに、ひとみさんへの脅迫や嫌がらせが始まった。傍聴席には毎回のようにヤクザ風の男たちが詰めかけ、威圧的な空気を作り出した。裁判所の外でも危険は続いた。自宅の前に待ち伏せされたり、駅のホームで電車を待つ間に突き落とされそうになるなど、日常的に身の危険を感じる出来事が繰り返された。事態を重く見た警察は、暴力団対策法に則り、ひとみさんを「要保護対象」として認定し、警護を強化した。彼女はいつしか警察関係者の間で「マルタイの女」と呼ばれるようになった。ひとみさんはこうした危険を顧みず、積極的にメディアの取材に応じ、娘を暴力団に奪われた悲痛な思いと、暴力団の理不尽さを社会に訴え続けた。その叫びは多くの人々の共感を呼び、社会全体に暴力団に対する厳しい目を向けさせるきっかけとなった。
膠着する審理:使用者責任と証言の壁
公判は当初から難航した。被告である組長は、事件への自身の関与を一貫して否定し、犯行は組員の独断によるものだと主張した。さらに、被告側の弁護人は、暴力団組長に使用者責任を問う訴えに対し、当時の使用者責任の時効(加害者を認識してから3年、現在は5年)が成立していることを盾に、ひとみさんの主張を退けようとした。審理が膠着した背景には、もう一つの大きな壁があった。娘を殺害した実行犯として有罪となった男が、民事裁判の原告側証人として出廷した際、面会時の話とは異なり、「組長の命令でやったのではない」と証言することを拒否したのだ。この証言拒否は、組長への使用者責任追及をさらに困難にした。
 イメージ写真:社会問題としての暴力団
イメージ写真:社会問題としての暴力団
和解勧告と断固拒否:娘の無念を晴らすために
審理が遅々として進まない状況を見かねた裁判所は、1994年に和解を提案した。しかし、若くして命を奪われた娘の無念を誰よりも深く感じていたひとみさんは、和解案に首を縦に振ることはできなかった。彼女にとって、和解は組長に罪を認めさせる機会を失うことを意味した。和解には断じて応じられない。一方で、暴力団関係者からの脅しや嫌がらせは日増しにエスカレートしており、彼女は常に危険と隣り合わせだった。民事訴訟は、使用者責任や時効の問題、証言拒否など、多くの法的・現実的な壁に阻まれながらも、ひとみさんの「暴力団撲滅」への強い決意によって続けられていった。
参考資料:『世界で起きた戦慄の復讐劇35』(鉄人社)より抜粋