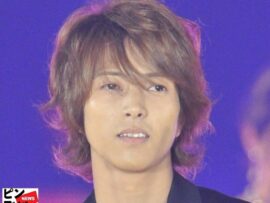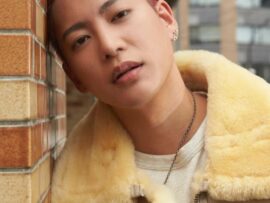近年、動画やドラマを倍速で視聴する習慣が広まっている。特に若い世代を中心に、限られた時間で多くのコンテンツを消費する「タイムパフォーマンス(タイパ)」を高める手段として定着しつつある。2024年の調査によれば、15歳から79歳の日本人のうち54.1%が「倍速視聴をすることがある」と回答しており、もはや多くの人にとって身近な視聴方法となっている。通勤・通学中や外出先の移動時間など、隙間時間を有効活用したいというニーズがその背景にある。しかし、この倍速視聴の風潮に対し、内科医である工藤孝文氏は警鐘を鳴らしている。タイパ向上に有効な一方で、私たちの心身に大きな負担をかけているというのだ。
倍速視聴には、タイムパフォーマンスの向上というメリットがある一方で、無視できない大きなデメリットが存在する。それは、交感神経の働きが過剰になり、自律神経のバランスが崩れてしまう可能性だ。最近の研究では、同じ動画を視聴した場合でも、通常速度で再生した場合と比較して、倍速再生時の方が交感神経の活動が高まることが確認されている。これは、一度に脳に入ってくる情報量が加速度的に増えることで、脳が強いストレスを感じるためだと考えられている。脳には情報処理、感情制御など、それぞれ異なる役割を持つ部位があるが、あまりに速すぎる情報流入はこれらの部位の処理能力を超え、脳を疲弊させてしまうのである。
また、倍速でコンテンツを消費することは、単に映像を目で追うだけの「ながら見」になりがちで、内容を深く理解したり、感動したりといった感情的な繋がりが希薄になるという側面もある。せっかく時間を使って視聴しても、何も心に残らないまま終わってしまうことになりかねない。さらに、常にせわしなく早口なナレーションやセリフを聞き続けることは、私たち自身の思考や行動もせかせかしたものに変えてしまう一因となり、新たな倍速行動を誘発する悪循環を生む可能性も指摘されている。
 現代の動画視聴習慣と画面を見つめる人物のイメージ
現代の動画視聴習慣と画面を見つめる人物のイメージ
では、この「倍速」の波に抗い、心身の健康を保つためにはどうすれば良いのか。工藤氏が提唱するのは、あえてペースを落とす「0.75倍速健康法」だ。もちろん、物語性が重要なドラマや映画を0.75倍速で視聴すると、テンポが崩れて楽しめなくなることがあるため、全てのコンテンツに適用する必要はない。特に0.75倍速での視聴が推奨されるのは、ストレッチなどの身体を動かすエクササイズ動画だ。YouTubeなどで公開されているストレッチ動画を0.75倍速にすることで、インストラクターの筋肉の微細な動きや呼吸のタイミングなどをより詳細に観察できるようになる。今まで漫然と行っていた動作も、「この動きの時はもっと脇腹を意識して伸ばすべきなのか」「足はこの角度に保つのが正しいのか」といった新たな発見に繋がり、より効果的なトレーニングに結びつく。
さらに、0.75倍速で身体を動かすことは、自然と呼吸もゆっくりになるため、副交感神経が優位になり、リラックス効果や精神的な落ち着きをもたらす効果も期待できる。ストレッチ以外では、スポーツの実況動画を0.75倍速で視聴することも興味深い。例えば、スピーディーなパス回しやドリブルが見どころのサッカーでも、あえて速度を落としてみることで、「あの選手はあんな体勢からボールを蹴り出していたのか」「パスを受ける選手は、あんなに離れた場所から走り込んでいたのか」といった、通常速度では見落としがちなプレーの細部が鮮明に見えることがある。これにより、まるで自分がそのスポーツの専門家になったかのような、より深い洞察や楽しみ方ができるようになる。
動画視聴だけでなく、日常生活に「ゆっくり」を取り入れることも重要だ。その手軽な方法の一つが、スローテンポの音楽を聴きながら散歩をすることである。音楽のテンポが人の心身に影響を与えることは広く知られている。一般的に、速いテンポの曲は心拍数を上げ、交感神経を優位にさせる傾向がある。運動会でおなじみの『天国と地獄』のような曲を聴くと、自然と心がせき立てられるような感覚になる人は多いだろう。反対に、ゆったりとしたクラシック音楽やヒーリングミュージックなどは、副交感神経を活性化させ、心身をリラックスさせる効果がある。
このように、現代社会で広がる「速さ」を追求する流れに逆らい、意識的にペースを落とす「0.75倍速」やその他の「ゆっくり」とした行動を取り入れることは、単にコンテンツの消費方法を変えるだけでなく、過剰になった交感神経の働きを抑え、自律神経のバランスを整えることにつながる。これは脳疲労の軽減やストレスの緩和にも寄与し、結果として私たちの健康と幸福度を高めるための有効な手段となり得るのだ。タイパを意識することも時には重要だが、心身の健康という視点から、意識的に「遅さ」の恩恵を見直す価値はあるだろう。