近年、コメの価格高騰と品薄が続き、「令和の米騒動」とまで称される事態が起きています。この状況に対し、料理研究家の土井善晴氏は、単なる不作や流通の問題だけでなく、現代日本人の食に対する根本的な意識に警鐘を鳴らしています。
「不作」は自然の摂理、備蓄米の活用を
土井善晴氏は、現在のコメ不足や価格高騰について、「お米は自然の恵みであり、年によって『不作』はあって当たり前」と指摘します。そして、その不作や価格高騰に備えて国があらかじめ買い入れ、保管しているのが「備蓄米」であると強調。今回の天候不順による米価高騰と不足に対し、備蓄米の出荷は「大問題だとは思いません」と述べています。
コメが例年よりも高価であることは望ましい状況ではありませんが、物価高騰はコメに限った問題ではありません。土井氏は、コメだけに焦点を当てて騒ぎ立てる風潮や、一連の政府・流通の対応の鈍さに「違和感を持っている」と語ります。
消費者は「おいしいお米」を本当に意識していたのか
土井氏は、現在のコメ不足と価格高騰、そして一連の流通対応の悪さが問題であるとしながらも、消費者への問いかけを投げかけます。「消費者は備蓄米を味の悪い米と決めつけ、『おいしいお米』を今まで通りの低価格で売ってほしいという。けれども、その『おいしいお米』を、あなたはちゃんと食べていましたか?」
現代社会では、外食や中食で食事を済ませたり、加工食品に依存する人々が増えています。そうした中で、「ふだん食べているご飯が『おいしいか、まずいか』をちゃんと意識できている人がどれだけいるか」と土井氏は疑問を呈します。メディアが「令和の米騒動」と煽る一方で、ここに来て突然「おいしいお米」を求める消費者の姿勢に、「おかしなもんやなあ」と違和感を覚えていると語っています。
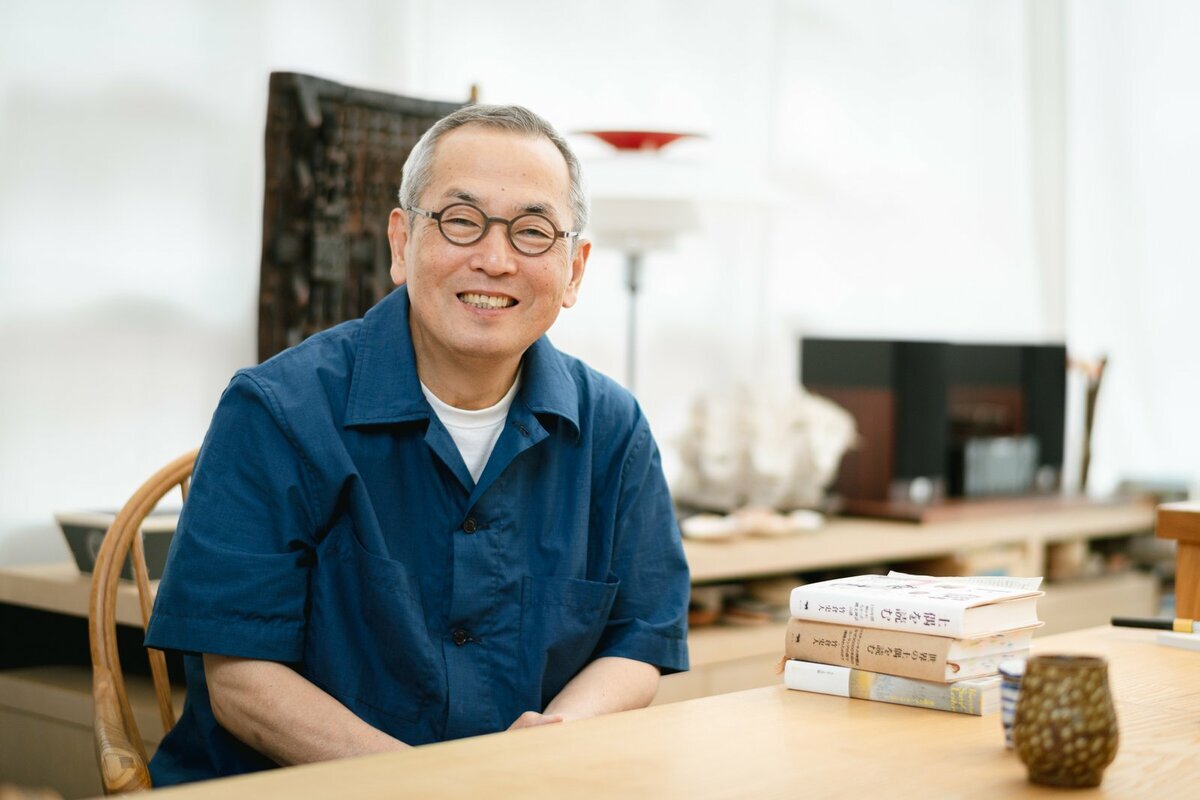 料理研究家 土井善晴氏の肖像。日本の米価格高騰と食糧問題について語る
料理研究家 土井善晴氏の肖像。日本の米価格高騰と食糧問題について語る
炊き方を知らない現代と失われたコメの価値
土井氏は、たとえ「古古米(ここまい)」であっても、おいしく炊くための基本的な手順を守れば十分に美味しくいただけると指摘します。具体的には、「水が澄むまで」洗い、ざるにあげて吸水させた「洗い米」を「きれいな水」で水加減し、「すぐ加熱する」といった米炊きの基本が重要であると説きます。味や風味に格別のこだわりがない限り、これだけで十分であると述べています。
実際に、土井氏が出張先のビジネスホテルの朝食で食べたご飯や、ロケ弁のご飯は、「私が炊いた古古古米よりぜんぜんおいしくない」と感じたと言います。多くの人は、言われなければご飯の味の良し悪しを意識せずに食べているのが現状かもしれません。業務用炊飯器の販売者によると、業務でご飯を炊く人でさえ、その炊き方を知らない人が多いため、販売は指導とセットになっているとのことです。コメのブランドや炊飯器の性能に頼るだけでは、決して「おいしいご飯」にはなりません。土井氏は、「米は日本人の主食ですが、いつの頃からか大切にされなくなっていたんです」と、現代日本におけるコメの価値の軽視に警鐘を鳴らしています。
結論として、今回の「令和の米騒動」は、単なる食糧問題だけでなく、日本人とコメとの関係性、そして食に対する意識そのものを見つめ直す機会であると土井氏は示唆しています。
Source: https://news.yahoo.co.jp/articles/61cb2ad757b7e9375a494a946679b33b813c14f8






