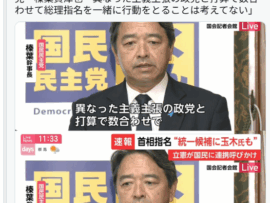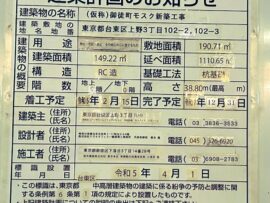NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で、物語の序盤からたびたび登場し、視聴者の間でその存在意義が議論されてきた人物、それが佐野善左衛門政言(矢本悠馬)です。徳川家に三河以来仕える旧家である佐野家の当主であり、かつては田沼意次(渡辺謙)の田沼家にとって主家筋にあたったこの政言が、最終的に田沼意知(宮沢氷魚)に斬りかかるという衝撃的な展開に至るまで、彼の行動とその背景にある「系図問題」が、物語の重要な伏線として機能していました。本記事では、政言がなぜ『べらぼう』に登場し続けたのか、その理由と、田沼意知襲撃事件の歴史的背景、そしてその衝撃的な結末を詳細に解説します。
佐野政言の登場と「系図問題」の伏線
佐野政言は、『べらぼう』第6回「鱗(うろこ)剥がれた『節用集』」で初めて登場して以来、断片的に描かれてきました。彼が当初見せた行動は、息子の田沼意知を通じて、田沼意次に佐野家の「系図」を献呈するというものでした。これは、田沼家の由緒を示すために自由に改竄して構わないから、代わりに佐野家を良い役職に取り立ててほしいという、いわば「猟官運動」でした。しかし、この申し出に対し、意次は激しいいら立ちを見せます。自身が足軽出身であることを度々揶揄されてきた意次は、「出自などにこだわるな」と言い放ち、その系図を池に投げ捨ててしまいます。
 大河ドラマ『べらぼう』で佐野政言を演じる矢本悠馬。彼の複雑な役どころが物語の鍵を握る。
大河ドラマ『べらぼう』で佐野政言を演じる矢本悠馬。彼の複雑な役どころが物語の鍵を握る。
この出来事以来、政言の登場シーンは散発的で、一部の視聴者は彼の登場が何のためなのか、物語にどう絡むのか疑問に感じていたかもしれません。しかし、第27回「願わくば花の下にて春死なん」で、その疑問は氷解します。政言が抱いていた田沼意知への恨みは、件の系図問題に加え、彼が持つ身分への執着と田沼家の台頭への複雑な感情が絡み合い、最終的に(誤解に基づく)深い憎悪へと発展していたのです。
天明の悲劇:江戸城内での若年寄襲撃
蓄積された恨みは、天明4年(1784年)3月24日、ついに思い切った行動へと政言を駆り立てます。将軍の警護役である新番士を務めていた政言は、その日、江戸城本丸御殿の表の詰所にいました。同じ本丸御殿表の御用部屋で政務を終え、廊下を退出していた若年寄の田沼意知に対し、政言は突然、大刀を抜いて斬りかかったのです。この一連の出来事は、江戸城という幕府の心臓部で起こった前代未聞の事件として、当時の社会に大きな衝撃を与えました。
続く第28回「佐野世直大明神」では、田沼家の上屋敷に運ばれた意知が手当の甲斐なく死去し、一方の政言は伝馬町の揚座敷(身分の高い囚人を収容する施設)で切腹を命じられます。
田沼意知が応戦できなかった背景と事件の衝撃
田沼意知が政言の凶刃に対して真っ当に応戦できなかったのには、当時の江戸城内における厳格な規則が深く関係しています。江戸城内では原則として帯刀が禁止されており、装飾的な脇差のみを差すことが許されていました。さらに重要なのは、その脇差でさえ、抜刀して応戦すれば「喧嘩両成敗」の原則により、たとえ正当防衛であっても処分され、相手を傷つければ死罪は免れないという厳しい掟があったことです。このため、意知は自らの脇差の鞘で政言の大刀を受け止めようとしましたが、肩先に骨まで達する深い傷を負ってしまいます。
周囲の同僚たちが次々と逃げ惑う中、意知は部屋に逃げ込みますが、追いかける政言の刀を両股にも受けてしまいます。最終的に、70歳を超える大目付の松平忠号が羽交い絞めにして動きを封じ、目付の柳生久通が刀を奪うことで、政言はようやく取り押さえられました。政言が将軍警護用の大刀を抜いたと見られるこの事件は、城内で抜刀した時点で死罪を覚悟していた行動であり、彼が田沼意知を亡き者にしようとした動機が、どれほど根深いものであったかを物語っています。
結び:大河ドラマが描く歴史の深層
佐野政言と田沼意知の物語は、単なる個人的な確執にとどまらず、旧来の家柄や身分に重きを置く社会と、実力主義によって台頭してきた田沼意次のような新しい勢力との間で生じた軋轢を象徴しています。大河ドラマ『べらぼう』は、佐野政言という一見謎めいた人物の存在を通じて、この時代の複雑な社会構造と、そこに生じた悲劇的な事件の深層を丁寧に描き出しました。
政言の行動は「誤解に基づく恨み」とされていますが、それは、変化する時代の中で自身の価値観や立場を見失い、焦燥感に駆られた個人の悲劇として解釈できます。彼の命をかけた行動は、田沼意次の改革路線に大きな打撃を与え、歴史の転換点の一つとして深く刻まれることになります。『べらぼう』は、この歴史的事件を人間ドラマとして深く掘り下げ、視聴者に多角的な視点を提供することで、時代劇の魅力を改めて示しました。