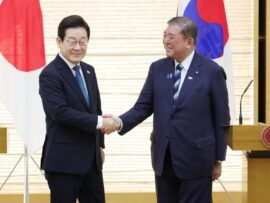日本の水道料金は世界的に見ても安価な部類に入り、梅雨や台風シーズンには大規模な水害が頻発し、近年はゲリラ豪雨による浸水被害も増加しています。こうした状況から、「日本は水が豊富な国だ」という認識を持つ人は少なくありません。しかし、これは大きな誤解であり、特に地下水に関する現実を知れば、その考えが根本的に覆されるでしょう。日本が過去に経験した地下水の過剰利用問題は、そのリスクを明確に示しています。
 豊かな水資源の国と思われがちな日本だが、地下水の有限性とその過剰利用がもたらす問題は深刻である。
豊かな水資源の国と思われがちな日本だが、地下水の有限性とその過剰利用がもたらす問題は深刻である。
地下水の過剰利用と過去の教訓
地下水の過剰利用は、かつて日本国内で深刻な社会問題を引き起こしました。昭和中期には、東京、大阪、名古屋といった大都市圏で大規模な地盤沈下が顕在化し、それに伴う湧水の枯渇や塩水の侵入といった問題が確認されました。これらは、主に工業用水や生活用水としての地下水の過剰な揚水が原因であり、そのリスクはすでに実証済みの歴史的な事実です。この記憶は、現代においてしばしば忘れ去られがちですが、地下水資源の持続可能性を考える上で極めて重要な教訓となります。
見過ごされがちな地下水の公共性と有限性
地下水は地中に存在するため、その実態が意識されにくく、しばしば軽視されてきました。中には「無尽蔵に存在し、枯渇することはない」という誤った認識で利用されるケースも散見されます。しかし、前述の通り、これは事実に反します。地下水は有限な水資源であり、その持続可能な利用のためには、明確な認識と適切なマネジメントが不可欠です。
あまり意識されていないかもしれませんが、地下水は地域社会を支える公共性の高い水資源です。その特徴としては、井戸から容易に得られる簡便性、他の水源と比べてコストが低い経済性、夏は冷たく冬は暖かい恒温性などが挙げられます。これらの特性から、地下水は生活用水、工業用水、農業用水として幅広く利用されるほか、豪雪地域では消雪用水としても重要な役割を担っています。
拡大する地下水需要と産業構造の変化
地下水の利用は公私にわたって多岐にわたります。公的な利用としては、水道水源に占める地下水(深井戸、浅井戸、伏流水を含む)の割合が約3分の1に達しています。また、私的な利用も増加傾向にあり、病院やホテルなどによる専用水道の届け出件数は、2002年の88件から2017年には1934件へと急増しました。
企業活動において「安定した水供給」は基盤の一つであり、特に工場などの生産現場では地下水が重要な役割を担っています。かつて水を大量に消費してきたのは化学工業、鉄鋼業、製紙業などでしたが、近年では産業構造の変化に伴い、新たな水使用者が台頭しています。例えば、データセンターの冷却水や半導体の洗浄水など、テクノロジー産業においても大量の地下水が使用されるようになっています。
結論:持続可能な地下水利用への意識変革
「水が豊富な国」という日本のイメージは、地下水の過剰利用によって引き起こされる深刻な問題を見過ごさせる危険性をはらんでいます。地下水は地域社会と産業活動を支える不可欠な資源であると同時に、その供給には限りがあります。過去の地盤沈下問題が示すように、安易な利用は将来にわたる環境負荷と経済的リスクをもたらします。日本が真の「水大国」であるためには、この有限な水資源である地下水に対し、より深い理解と責任ある持続可能な利用に向けた意識変革と具体的な対策が喫緊の課題と言えるでしょう。