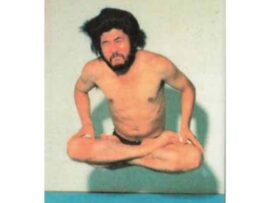今年7月の参議院選挙で、他の野党が議席を伸ばす中、立憲民主党は22議席の現有維持に留まり、党がまとめた総括文書ではその結果を「事実上の敗北」と明記しました。この「敗北」という言葉への修正は、党内からの「野田佳彦執行部は敗北を認めよ」という強い突き上げによるものとされています。しかし、ジャーナリストの尾中香尚里氏は、この党において「敗北の総括」は党を強化するどころか、党内抗争という後ろ向きのエネルギーを生み出し、かえって党を弱体化させてきたと指摘します。その背景には、「壊し屋」と評されるベテラン政治家、小沢一郎氏の存在が深く関わっていると尾中氏は分析しています。
参院選「事実上の敗北」が示す党内対立の根深さ
立憲民主党は先の参院選で議席を伸ばせず、その結果を「事実上の敗北」と総括せざるを得ませんでした。通常、選挙結果の総括は党の結束を固め、次なる戦略を練るための重要なプロセスです。しかし、立憲民主党の場合、この「総括」が常に党内抗争の火種となり、新たな「神輿」を求める動きや執行部への無責任な突き上げを生み出してきました。このような内向きのエネルギーは、党の成長を阻害し、むしろ弱体化を招く要因となっています。
「壊し屋」小沢一郎氏が立憲民主党を蝕む構造
党の弱体化の根本原因として、ジャーナリストの尾中香尚里氏が指摘するのは、政界の「壊し屋」として知られる小沢一郎氏の存在です。小沢氏は、「政権さえ取れれば理屈はどうでも良い」という姿勢で党の政治理念をねじ曲げ、他の野党との選挙協力を重視するあまり、自らの党の成長を阻害してきた経緯があります。そして、結果として党が弱体化すれば、新たな執行部を求める「執行部おろし」をけしかけるというパターンを繰り返してきました。メディアが無批判にこの動きを持ち上げ、非執行部系議員による執行部批判に追い風を吹かせる構図は、新進党、民主党に続き、立憲民主党においても再現されていると尾中氏は警鐘を鳴らします。小沢氏自身が「政権交代可能な政治」の阻害要因となっていることに、そろそろ気づくべきだという厳しい意見も投げかけられています。
 立憲民主党の幹部が戦略や政策について話し合う会議の風景
立憲民主党の幹部が戦略や政策について話し合う会議の風景
消費減税公約の強制:小沢氏の「最大の罪」
参院選における小沢氏の「最大の罪」と尾中氏が断じるのは、「消費減税を公約に掲げさせた」ことです。今年2月、党の総合選挙対策本部長代行であった小沢氏は、消費減税について「食料品だけではない。もっと大きくやらないとダメだ」と主張し、党内の「消費減税論争」を激化させました。党が5月に参院選の公約として「食料品の消費税率を原則1年に限りゼロ」という方針を打ち出すと、小沢氏は「効果が疑わしい」と不満を露わにしました。
しかし、立憲民主党は前年秋の代表選で、消費減税を巡る議論を経て、減税に最も慎重だった野田氏を代表に選出しています。その1カ月後に行われた衆院選では、消費減税を掲げることなく選挙戦を戦い、50議席増という躍進を果たしました。この時、自民・公明連立与党は過半数割れを起こし、立憲民主党の国会での存在感は大きく増していたのです。本来、消費減税問題は、党内手続き的にも、総選挙での民意の審判という点でも、次の代表選までは決着がついている問題であったはずでした。
小沢氏らの突き上げにより、党内融和を無視できなくなった野田氏が消費減税に言及し「ぶれる」形となったことで、立憲民主党のコアな支持層や、自民党に代わる責任政党を求める無党派層の支持が崩れ、衆院選で得た党の勢いを食い潰してしまったと尾中氏はみています。
「責任政党」としての立憲民主党と消費減税の矛盾
尾中氏は、消費減税を主張する政党の存在自体を否定しているわけではありません。それを望む国民がいる以上、政権を担う責任を負わない中小政党が、国民の生活の苦しさを代弁し、国会で政府に伝える役割を果たすことには意味があります。
しかし、政権の中核となることを求められる「責任政党」、つまり自民党と立憲民主党は、中小政党と同じ役割に甘んじてはいけません。国民の痛みを受け止めつつも、安易に大きな税収を失うことができない現実を見据え、給付付き税額控除のような別の策を駆使して痛みの軽減を図り、それを国民に誠実に訴えるべきだと尾中氏は主張します。
ましてや立憲民主党は、新自由主義から脱却し「公」の役割を拡大して再分配によって格差縮小を図ることを掲げる政党です。これは自民党との重要な対立軸でもあります。そのような理念を持つ政党が安易に消費減税を訴えれば、党が掲げる他のすべての政策の実現性が疑われ、有権者の信用を失いかねません。
立憲民主党は、すでにその他の中小政党とは役割が全く異なります。せっかく衆院で「2強多弱」の状況を作り出し、責任政党としての立場を確立しつつあるのに、消費減税を叫ぶことは、その果実を自ら手放し、中小野党と同じ立場に「降りる」、即ち政権交代を諦めることと同じであると尾中氏は厳しく批判します。小沢氏がこの本質的な問題を理解していないことが、立憲民主党の苦境を深めているとの見解です。
結論
立憲民主党が参院選で「事実上の敗北」を喫した背景には、長年にわたる党内抗争と、特定のベテラン政治家による党の理念にそぐわない政策の押し付けが大きく影響しています。「壊し屋」と称される小沢一郎氏が消費減税を公約に掲げさせたことは、党が「責任政党」として確立しつつあった立場を自ら危うくし、国民からの信頼を損なう結果を招きました。立憲民主党が真に政権交代可能な政党として国民の期待に応えるためには、党内融和を図り、政党としての明確な理念と現実的な政策を両立させることが不可欠です。内向きの争いを乗り越え、国民の生活に資する政策を真摯に追求する姿勢が、今、最も求められています。
参考文献
- PRESIDENT Online: 「壊し屋」小沢一郎が立憲を壊しにかかっている…参院選で立憲民主党の足を引っ張った「消費減税」の責任 (https://president.jp/articles/-/61667)
- Yahoo!ニュース: 「壊し屋」小沢一郎が立憲を壊しにかかっている…参院選で立憲民主党の足を引っ張った「消費減税」の責任 (https://news.yahoo.co.jp/articles/e611471512120179e4ce74dd989cc637a7e4ef43)