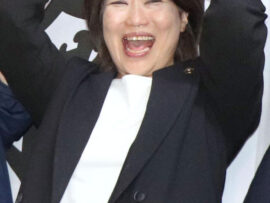政府は外国人観光客による「爆買い」が日本経済を潤すと信じ、「観光立国」戦略を推進しています。しかし、インバウンド需要の拡大がGDPや旅行業界の売上を伸ばしても、日本国民の暮らしは本当に豊かになるのかという疑問が浮上しています。むしろ、外国人消費に過度に依存する国は、やがて大きな代償を払うことになるという専門家の警鐘も鳴らされています。私たちの生活はどうなってしまうのか?いま注目のエコノミスト、河野龍太郎氏と唐鎌大輔氏が、共著『世界経済の死角』から、この重要な問いに深く切り込みます。彼らの分析は、表面的な経済指標の裏に隠された、インバウンド経済の真の姿を明らかにします。
「観光立国」戦略の功罪:見せかけの「生産性向上」と国民の生活
日本のGDPにおける「非居住者家計の国内での直接購入」、いわゆる「インバウンド消費」の存在感は近年、飛躍的に高まっています。現在の政権も前政権の路線を引き継ぎ、地方創生の文脈から観光産業の活性化を後押しする姿勢を打ち出しており、インバウンドを日本経済浮揚の起爆剤と捉える見方が一般的です。しかし、エコノミストの唐鎌大輔氏は、この「観光立国」戦略だけで日本経済の真の豊かさを実現できるのかに疑義を呈します。彼は、海外からの旅行者に日本人の労働力を安く提供する現状が、果たして国民の豊かさに繋がるのか、冷静な議論が必要だと訴えます。
唐鎌氏は、宿泊・飲食業界を中心として、インバウンド需要の高まりに応じて「生産性向上」が報告される一方で、多くの場合、起きているのはただの「単価上昇」に過ぎないと指摘します。同じ財やサービスをより高い値段で売るようになっているため、統計上は「生産性が上がった」ということになりますが、これは本質的な生産性の改善とは異なります。彼自身の経験として、都心の高級寿司店の値段がこの10年ほどで、倍どころか3、4倍ほどになっているケースも珍しくないと言います。唐鎌氏自身が鮨職人などとの交流で得た知見として、「生産性=付加価値÷労働投入」の分母(労働投入)は大きく変わらず、分子(付加価値)を大きく引き上げている例が多数あると感じたと言います。仕入れ値やアルバイト時給上昇だけでは説明できない単価上昇は、まさに「インバウンドの財布に合わせている」結果であり、日本人と扱いを変えるためにインバウンド専用の予約日を設ける店もあるほどです。こうしたマージンの上乗せが統計上の生産性改善に繋がるものの、これは多くの国民が期待する真の経済的恩恵とはかけ離れた現実です。
 インバウンド消費による繁華街の賑わいを背景に、日本経済への影響を考察するイメージ
インバウンド消費による繁華街の賑わいを背景に、日本経済への影響を考察するイメージ
円安下の日本経済:実質賃金停滞のメカニズムと未来への警鐘
エコノミストの河野龍太郎氏は、近年のインバウンドの拡大を「日本経済にとって手放しで喜べない現象」だと捉えています。彼が指摘するのは、ヨーロッパで暮らす人々が日本を旅行する際に感じる「あまりの安さ」であり、まるでタイムマシンに乗って25年前、30年前の世界に舞い戻ったような感覚を抱くという点です。この感覚の背後には、「生産性が上がっているのに、実質賃金がまったく上がっていない」という、日本特有の根深い状況が存在します。
具体的に見てみると、日本よりも生産性の改善が劣るヨーロッパ諸国でさえ実質賃金はアメリカほどではないにせよ、着実に改善しています。これに対し、日本だけが「生産性の向上」と「実質賃金の上昇」が乖離したままかみ合っていないのです。河野氏は、長年にわたって物価が上がらなかった理由についても、従来の多くのエコノミストの見解に疑問を呈します。彼は、「生産性が上がらなかったから、実質賃金が上がらず、物価も上がらなかった」という因果関係ではなく、真の因果関係は「生産性が上がっても、賃金が上がらなかったから、その分、物価上昇が抑えられてきた」というものであったと分析します。この結果、円が弱くなった日本は、外国人消費によってまるで「食い荒らされる」ような状況に陥っていると警鐘を鳴らしており、国民の豊かさに直接結びつかない経済成長の姿を浮き彫りにしています。
結論
インバウンド消費の拡大は、一見すると日本経済に好影響をもたらす一方で、専門家は多くの課題を指摘します。表面的なGDP成長や観光収入増加の裏で、国民の生活は豊かにならず、むしろ物価の上昇や実質賃金の停滞という代償を払う可能性があります。真の「観光立国」とは、単に外国人を呼び込むだけでなく、国民一人ひとりの生活が実質的に向上する経済構造の構築を意味します。日本経済の持続的な成長のためには、インバウンドに過度に依存しない、より多角的な視点での政策と戦略が求められます。
出典: 河野龍太郎、唐鎌大輔『世界経済の死角』(幻冬舎)より抜粋・編集