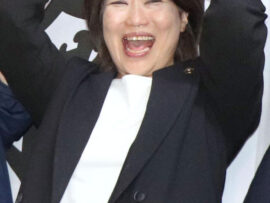将棋界のプロフェッショナルとして、そして藤井聡太七冠の師匠としても広く知られる杉本昌隆八段。11歳で故・板谷進九段の門下に入り、プロデビューから今年で35年を迎えます。50歳を超えてもなお昇級を続け、「中年の星」と称される彼の現役棋士としての活躍は、多くの人々に勇気を与えています。特に、40代後半から試みているという技術を伸ばす「秘策」について、ジャーナリストの笹井恵里子氏が詳細を尋ねました。これは、年齢を重ねてもなお成長し続けるための貴重なヒントとなるでしょう。
50代からのキャリア変革:体力の衰えを受け入れ、新しい自分を創造する
50代後半に入り、杉本八段自身も体力のピークが過ぎたことを実感していると言います。かつて40代の頃は2日間徹夜しても平気だった体も、今はそうはいきません。しかし、「あの頃はできたのに」と過去を振り返って苦しんだり、変化を拒否したりするのではなく、新しい自分を生み出すためには、この変化を積極的に受け入れることが重要だと語ります。常に同じことを繰り返しているだけでは、いずれ行き詰まってしまう可能性が高いのです。40代や50代になると、自分の得意分野や強みが明確になり、長年培ってきたものからなかなか脱却できないと感じる気持ちは理解できます。経験も豊富で、得意なことだからこそ、それを使い続けてしまいがちです。
長年の「強み」からの脱却:得意戦法「振り飛車」40年の変化
杉本八段自身も、将棋の「振り飛車」という戦法を15歳の頃から使い始め、すでに40年間も愛用してきたと明かします。これは彼のプレイスタイルの中核をなす「強み」でした。
藤井聡太七冠がもたらした転機:40代後半からの「新戦法」導入
しかし、驚くべきことに、杉本八段は40代後半から“新しい戦法”を取り入れるようになったのです。これを野球に例えるなら、これまで変化球投手だったのが、新たにストレートを投げ始めたようなものだと言います。最初は研究会といったトレーニングの場で試し、徐々に公式戦で実践投入するようになりました。現在では、従来の得意戦法を採用する比率は大幅に減り、実戦では3〜4割程度にまでなっています。この変化の大きなきっかけとなったのは、弟子の藤井聡太七冠の影響かもしれません。
「安全な勝利」から「リスクを恐れぬ挑戦」へ:師弟の対照的なスタイル
杉本八段は元々、「安全に勝つ」ことを好む棋士でした。わずかにリードを奪い、その差を広げようとせず、優勢な状態を保ったまま終局へと向かうスタイルです。結果として手数が長くなり、対局も長時間に及びました。しかし、体力には自信があったため、これを武器に長期戦で“体力勝ち”を収めるような将棋を指していました。先輩棋士からは「杉本くんは“良い手”は全然指さないけれど、終わったら勝っているよね」と冗談交じりに言われることもあったそうです。なぜそう見えるのか、杉本八段自身もよく理解していました。「良い手を指す」ということは、相手と“斬り合う”ことにも繋がり、リスクが高いと感じて避けていたからです。そのため、同じ状態を維持することを重視していました。もちろん、これも一つの戦法であり、彼が八段まで昇り詰めたことからも、間違っていたとは考えていません。
 盤面を熟考する将棋の杉本昌隆八段
盤面を熟考する将棋の杉本昌隆八段
ところが、弟子の藤井七冠は、師匠である杉本八段とは全く逆のスタイルを持つ棋士なのです。
杉本昌隆八段のキャリアは、年齢や経験にとらわれず、常に変化と挑戦を受け入れることの重要性を示しています。特に40代、50代といった節目を迎える人々にとって、体力の変化を受け入れ、長年の「強み」に固執せず、新しい知識や技術を積極的に取り入れる姿勢は、キャリアを豊かにし、人生を活性化させるための大きなヒントとなるでしょう。藤井聡太七冠との師弟関係が、互いの成長を促す触媒となっている点も、学びの継続と多角的な視点を持つことの価値を教えてくれます。私たちも、杉本八段のように「中年の星」として輝き続けるために、変化を恐れず、新たな一手を指す勇気を持ちたいものです。