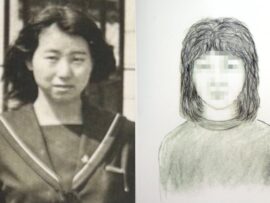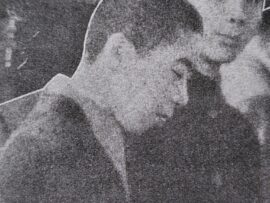NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第42回「招かれざる客」(11月2日放送)は、多くの視聴者に衝撃を与えました。主人公である稀代の版元・蔦屋重三郎(横浜流星)と、人気絵師・喜多川歌麿(染谷将太)の間に生じた決定的な亀裂は、単なるビジネス上の衝突を超え、芸術家の「矜持」と商業的成功の「葛藤」という深遠なテーマを浮き彫りにしています。このエピソードは、なぜ歌麿が蔦重のもとを離れることになったのか、その舞台裏と史実に基づいた背景を深く探る上で極めて示唆に富んでいます。
蔦重の「無茶な要求」と歌麿の「創作へのこだわり」
歌麿が描いた美人大首絵、特に当時の江戸で絶大な人気を博した『当時三美人(寛政三美人)』が大ヒットを記録し、耕書堂には歌麿に絵を描いてほしいという商人が列をなしました。しかし、喜びも束の間、大量の注文に悲鳴を上げる歌麿に対し、蔦重は「弟子に描かせたらどうだ?」「お前が名だけ入れりゃあいい」と提案。一枚一枚丁寧に描きたいという歌麿の抵抗を、「お前の絵はお江戸の不景気をひっくり返しはじめてんだよ。ちょいとした方便くれえ、お前、許されんだろ?」と一蹴しました。
さらに蔦重は、吉原の遊女絵の揃いもの企画を持ちかけ、歌麿が50枚描くことで、蔦重が吉原に負っている100両の借金が返済されるという取引を勝手に進めます。この事態を知らされた歌麿は激怒し、「それ、借金のかたに俺を売ったってこと?」と詰め寄りました。蔦重は礼金も払うと釈明し、妻ていの妊娠や新たな売れ筋が必要な窮状を訴えますが、自分に何の相談もなく仕事内容を決められた歌麿の怒りは収まりませんでした。この一連のやり取りは、商売のためなら手段を選ばない蔦重の強引な一面と、芸術家としての創作へのこだわりを持つ歌麿の間に横たわる深い溝を浮き彫りにしました。
 大河ドラマ「べらぼう」で蔦屋重三郎を演じる横浜流星。その厳しい表情は、歌麿との関係性の変化を示唆する。
大河ドラマ「べらぼう」で蔦屋重三郎を演じる横浜流星。その厳しい表情は、歌麿との関係性の変化を示唆する。
史実が語る「決別」の背景:版元と絵師の「力関係」
結局、歌麿は蔦重の仕事を引き受けますが、自己中心的な要求を繰り返す蔦重に対する不信感は募るばかりでした。そのような中、別の版元である西村屋の二代目・万次郎が歌麿を訪れます。以前は断っていた万次郎からの依頼を、歌麿は「この揃いものを描き終わったら、もう、蔦重とは終わりにします」と告げて快諾しました。これは、ドラマの中だけでなく、史実においても歌麿と蔦重の関係に終止符が打たれる時期と重なります。
史実では、歌麿は寛政6〜7年(1794〜95年)ごろから、蔦重とは距離を置き、若狭屋、岩戸屋、近江屋といった他の多くの版元から錦絵を刊行するようになります。その理由の一つとして、蔦重のもとから刊行された歌麿の美人画には必ず、「歌麿筆」という署名の上に蔦屋の印が押されていたことが指摘されています。これは、作品が歌麿の筆によるものである以前に、蔦屋が企画したものであることを示すものであり、世間に対し蔦屋の方が格上であるというアピールでもありました。
松嶋雅人氏は著書『蔦屋重三郎と浮世絵』の中で、「まだ売れていないうちならいざ知らず、人気がでれば自分はもっとこんな絵が描きたい、こんなふうに描いてみたいと思うもの。浮世絵は版元優先とはいえ、歌麿は我慢ならなかったのでしょう」と述べています。この指摘は、歌麿の芸術家としての自負心が、版元の商業的圧力と力関係の中で頭をもたげ、決断を促したことを示唆しています。
結論
大河ドラマ『べらぼう』が描く蔦屋重三郎と喜多川歌麿の決別は、単なる人間関係の破綻ではなく、江戸時代の浮世絵界における芸術家の創造性と版元の商業的戦略との間の普遍的な葛藤を象徴しています。蔦重の「無茶な要求」は、商業的成功への強い執念からくるものでしたが、それは同時に歌麿の芸術家としてのアイデンティティを踏みにじる行為でもありました。
このエピソードは、現代社会においても、ビジネスとクリエイティブの狭間で揺れ動く多くの人々にとって、示唆に富むメッセージを投げかけています。芸術家の「矜持」がどのように商業の波に抗い、あるいは妥協しながら新たな道を切り開いていくのか。『べらぼう』は、その問いを私たちに突きつけ、歴史の奥深さを再認識させてくれるでしょう。
参考文献:
- NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』公式サイト (https://www.nhk.or.jp/berabou/)
- 松嶋雅人『蔦屋重三郎と浮世絵』NHK新書
- Yahoo!ニュース記事 (https://news.yahoo.co.jp/articles/98d79df382109f77e79db75092d08fbff92903f9)