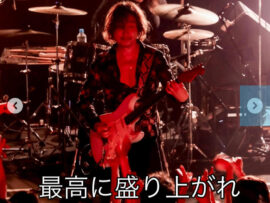7月20日に投票日を迎える参議院選挙において、参政党の勢いが注目を集めています。特に、代表の神谷宗幣氏による「高齢の女性は子どもが産めない」といった発言が強い批判を浴びたにもかかわらず、その後の支持率がむしろ上昇している現象は、政治アナリストや有権者の間で議論の的となっています。本記事では、この特異な現象の背景と、現代の政治潮流におけるその意味を探ります。
参政党、参院選での躍進とその背景
参政党は、6月下旬の都議選で候補者4人中3人が当選するなど、地方選挙での成功を足がかりに勢いを増しています。共同通信が参院選公示直後の7月5日、6日に行った比例代表選の投票先調査では、自民党に次ぐ二番手に躍り出るという驚くべき結果を示しました。これは多くの人々に衝撃を与え、参政党の存在感を一気に高めました。
しかし、この躍進と時を同じくして、公示日の7月3日には神谷宗幣代表が街頭演説で「高齢の女性は子どもが産めない」「男女共同参画は間違えた」などの発言を行い、各方面から強い批判を浴びました。通常であれば、このような物議を醸す発言は支持率に悪影響を与えかねないものですが、参政党の場合は異なる結果を示しました。
発言後の支持率変動:男性支持者の顕著な増加
神谷代表の一連の発言があった後、参政党の支持率はむしろ上昇傾向にあります。NHKが行った世論調査の結果を比較すると、この傾向は明らかです。参院選公示前の6月27~29日に行われた調査では、参政党の支持率は3.1%で、自民党、立憲民主党、国民民主党、公明党に次ぐ5位でした。ところが、神谷氏の発言があった直後の7月4~6日の調査では4.2%に上昇し、自民党、立憲民主党、国民民主党に次ぐ4位に浮上しました。
特に注目すべきは、この支持率上昇を牽引した層です。わずか1週間程度の間に、男性の支持率が3.9%から5.8%へと急伸していることが明らかになりました。この間、女性の支持はわずかに減少しています。結果として、男性の支持率は女性の約3倍となり、神谷氏の発言前までの約2倍からさらに差が広がりました。
その後、7月11~13日に行われた最新の調査では、参政党の支持率はさらに5.9%にまで上昇し、今や自民党、立憲民主党に続く3位に位置しています。この調査でも男性の支持率は7.6%へと跳ね上がりましたが、今回は女性の支持率も上昇したため、最終的に男性の支持率は女性の約2倍に落ち着いています。
 参議院選挙公示後、記者団の取材に応じる参政党の神谷宗幣代表
参議院選挙公示後、記者団の取材に応じる参政党の神谷宗幣代表
「新しいポピュリズム」と「炎上商法」の戦略
社会学者の伊藤昌亮氏は、7月8日のポリタスTVでのトークにおいて、「石丸現象や衆院選での国民民主党の飛躍など、その時の雰囲気でふわっと票が動いていく新しいポピュリズムが起きている。比較的若い男性の支持が流れていく傾向が強い。そうした動きが今回参政党に来ている」と指摘しています。前述の共同通信の調査でも、30代以下の若年層の男性で参政党を参院選の投票先に挙げた人々が国民民主党や自民党を抑えてトップに立つという結果が出ていました。さらに約1週間後のNHKの最新調査では、30代以下だけでなく60代まで、参政党への幅広い支持が広がっていることが示されています。
伊藤氏はまた、神谷氏の発言がある種の「炎上商法」であると分析しています。衆院選前、国民民主党の玉木雄一郎代表が尊厳死の法制化に言及し、多くの批判を浴びながらも話題を集め、結果として国民民主党も支持を大きく伸ばしました。神谷氏は、まさにそのような経緯に倣っている可能性が指摘されます。
実際に、神谷氏はその後、尊厳死ならぬ終末期延命措置の全額自己負担を提言し、再び物議を醸しました。そればかりでなく、外国人の待遇などを巡る神谷氏や参政党候補者の発言に対して、新聞やテレビ各社がファクトチェックを行う事態が相次いでいます。こうした中で、「高齢女性発言」のインパクトは相対的に薄まる形となっています。
しかし、「石丸現象」や「国民民主党現象」に続く「参政党現象」とも言うべき今回の動きで、支持者が急増しているのが男性であるにもかかわらず、メディアの言説が女性支持者に焦点を当てることが多いのは興味深い点です。これは、特定の層の動向が見過ごされている可能性を示唆しています。
結論
参政党の支持率が神谷代表の「高齢女性は子どもが産めない」発言後に上昇した現象は、現代の日本政治における「新しいポピュリズム」の台頭と、「炎上商法」とも呼べる戦略の効果を示唆しています。特に男性支持層、若年層から高齢層までの幅広い層からの支持拡大は、既存政党への不満や、特定のメッセージに共感する層の存在を浮き彫りにしています。今後も参政党の動向、そして批判的な発言が有権者の投票行動に与える影響については、引き続き注視が必要です。現代社会における情報伝達のあり方と、それが政治に与える影響を深く理解することが求められます。
参考文献
- 共同通信社
- NHK世論調査
- ポリタスTVにおける社会学者・伊藤昌亮氏のトーク (2025年7月8日)
- Yahoo!ニュース (記事提供:共同通信社)