百貨店のお客様相談室長として数々の難題を解決に導いてきた関根眞一氏は、まさに苦情対応のプロフェッショナルです。近年、日本社会で深刻化する「カスタマーハラスメント」、通称「カスハラ」は、単なる迷惑行為を超え、従業員の精神を蝕み、時には離職にまで追い込む社会問題となっています。本記事では、その関根氏が著書で明かした衝撃的な事例に焦点を当てます。ある書店で繰り広げられた悪質なクレーマー「E氏」による「カスハラとセクハラの二重苦」の実態と、プロがどのようにしてこの“カスハラの王様”に立ち向かったのか、その詳細と教訓を紐解きます。この事例は、日本における顧客対応のあり方と従業員保護の重要性を改めて問いかけます。
隠蔽された書店での「二重苦」:カスハラとセクハラの長期被害
「なぜこんな大事なことを、もっと早く言わなかったんだ!」――お客様相談室長の関根氏が、書籍売り場の社員を厳しく問い詰めたのは、現場で長期間にわたり繰り返されてきた「カスハラ」、さらには「セクハラ」とも解釈できる事案が、適切に処理されずに放置されていた事実が発覚したためでした。被害を受けていたのは30代前半の男性客、E氏によって困らせられ、泣かされているという女性社員たちです。
店長や総務担当に当時の状況を問いただすと、E氏から事前に「この女性が嘘を伝えて私を翻弄し、無駄な時間を費やしたため文句を言っている。上司であっても出る幕ではない、この女性が悪いのだ」と釘を刺され、対応をためらっていたことが明らかになりました。その結果、E氏の巧妙な心理的攻撃と威圧により、すでに2名の販売員が精神的苦痛から職場放棄に近い形で退職に追い込まれていました。しかも、この悪質な被害は実に3年間にもわたって続いていたのです。従業員の保護が全く機能していなかった現状に、関根氏は深い憤りを感じ、即座に本格的な対策に乗り出すことを決意します。
悪質クレーマー「E氏」の特定と「出入り禁止」への道のり
事件の深刻さを認識した関根氏は、翌日、旧知の書店役員、本部の部長、そして当該店舗の店長と総務担当の計4名を招集し、E氏への対応策について協議を開始しました。会議の冒頭、関根氏はE氏の「氏名、年齢、住まい、そしてその正体」を把握しているかを確認しました。E氏については「Eというようです」という程度の情報しかなく、本格的な対策には程遠い状況でした。
役員は「できれば追い出したい」と本音を漏らし、関根氏も「そうでしょう、出入り禁止にしましょうよ」と同意します。店舗への「入店規制」や「出入り禁止」は、事案の内容や悪質性によっては十分に可能な措置です。しかし、問題はE氏と対等に話せる「度胸のある社員」が一人もいなかったことです。そこで、過去の悪質な事例を具体的にまとめた文書を参照し、それに基づいて対応を進めることになりました。関根氏は、その温情的に書かれた書類だけではE氏を退けられないと直感しましたが、まずは「敵を知る」ために、E氏が引き起こした事例について詳細に読み込み、徹底的に予習しました。この専門家としての事前の準備こそが、後の攻防戦における重要な布石となります。
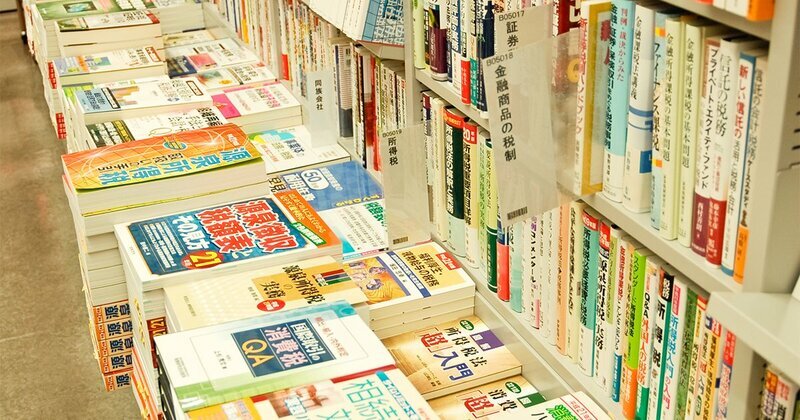 悪質なカスタマーハラスメントに直面する顧客対応担当者のイメージ
悪質なカスタマーハラスメントに直面する顧客対応担当者のイメージ
「カスハラの王様」E氏の具体的な手口:書店を舞台にした心理的攻撃
この「カスハラ」事件が起きたのは2000年代初期の頃であり、当時はまだ「カスハラ」という言葉自体が一般に浸透していませんでしたが、その実態は既に存在していました。E氏は、まさに「いじめが趣味」と称されるべき人物であり、その巧妙な手口から「カスハラの王様」と呼ぶにふさわしい悪質性を持っていました。現在では、国がカスタマーハラスメントに対する規制を設け、各都道府県が条例や規則を整備しているため、悪質な顧客の「出入り禁止」はより容易に行えるようになっていますが、当時はまだその意識も制度も未熟でした。
E氏のカスハラ手口は非常に巧妙で、以下のようなものでした。彼は書店に来店し、担当者が若い女性であることを見計らいます。標的を定めた後、例えば山岡荘八著『徳川家康』の単行本全26巻の棚に目をつけます。多くの書店では、このような多巻の単行本の場合、1~3巻あたりは棚に2冊ずつ展示し、売れても同巻が残るようにし、残りの巻は各1冊ずつ並べる簡略化された在庫管理を行っています。そして、棚の奥や下にある引き出しに同じ本を在庫として保管しているのが一般的です。
E氏はまず、棚にある2冊のうち1冊を別の棚に移動させ、しばらく担当者の様子をうかがいます。担当者が離れた隙に、もう1冊を非常に分かりづらい場所に隠します。さらに、在庫の引き出しを開けて在庫がないことを確認してから、その女性社員に声をかけるのです。「山岡荘八の徳川家康の単行本で、2巻を探しています。出張で時間がないのですが」と尋ねます。女性社員は「はい、こちらにあります」と答えるものの、あるべき場所に本が見当たりません。慌てて「少々お待ちください」と声をかけ、必死に探し回ります。E氏自身は素知らぬ顔で別の棚の単行本を見ているだけです。女性社員は30分前には確かに2冊あったはずだと思い込み、焦燥感に駆られながら探し続ける羽目になるのです。
社会問題としてのカスハラ:従業員保護と毅然とした対応の重要性
百貨店のお客様相談室長として数々のトラブルを解決してきた関根眞一氏が明かしたこの書店での事例は、単なる迷惑行為にとどまらない「カスハラ」の深刻な実態を浮き彫りにしています。特に、悪質なクレーマーが巧妙な手口で従業員の精神的負担を増大させ、ひいては離職にまで追い込むという事態は、日本社会全体が直面している課題と言えるでしょう。
このケースが示すのは、企業や組織が従業員保護のために、早期の介入と「カスハラ」に対する毅然とした対応がいかに重要であるかという点です。顧客対応のプロである関根氏の介入と、具体的な対策への動きは、このような問題に立ち向かう上で不可欠な専門知識と経験の価値を証明しています。日本ニュース24時間では、この事例を社会問題の一つとして捉え、全ての企業が従業員の安全と健全な職場環境を確保するための意識向上と対策強化の必要性を強く訴えます。
参考文献
- 関根眞一『カスハラの正体〈完全版〉となりのクレーマー』(中公新書、中央公論新社)
- Yahoo!ニュース(ダイヤモンド・オンラインより)- https://news.yahoo.co.jp/articles/405c02e8034af4159e448fc5d343d52ed7e1568e






