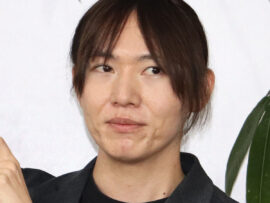「大学受験」は、日本の10代にとって人生最大の節目の一つであり、その後のキャリアや人生の選択肢を大きく左右する現実があります。良い大学への進学が、希望する職業に就ける確率を高め、将来の可能性を広げる一助となるのが現代日本の社会構造です。この度、複雑な時代における「自分らしい大学進学」を模索するための書籍『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売され、大きな注目を集めています。本記事では、発刊を記念し、著者であるびーやま氏への特別インタビューを通じて、「なぜ学歴が社会で重視されるのか」という根源的な問いに対する洞察を深掘りします。
若年層における「学歴」の持つ意味
社会では「高学歴だから成功する」「低学歴だから失敗する」といった単純な図式が常に当てはまるわけではありません。高学歴でも挫折する人はいますし、逆に学歴に関わらず成功を収める人も多く存在します。それにもかかわらず、なぜ日本では学歴が重要視されるのでしょうか。びーやま氏はこの問いに対し、「若い年齢のうちはそれが分かりやすい実績だから」と指摘します。
確かに社会に出れば、学歴以上に仕事の成果や実務経験が重視されるようになります。東大卒だからといって必ず成功するわけではなく、またFラン大学出身だからといって絶対に失敗するわけでもありません。結果を出せば、それが社会における評価に直結するのが現実です。近年の転職トレンドを見ても、この点は明らかです。しかし、20代のような職務経験がまだ少ない時期においては、個人を評価する明確な指標が少ないため、学歴が「将来への期待」という形で評価される傾向にあるとびーやま氏は解説します。
 日本の学生が机で勉強する様子。学歴とキャリア形成の重要性を示唆するイメージ。
日本の学生が机で勉強する様子。学歴とキャリア形成の重要性を示唆するイメージ。
学歴以外の「実績」の評価軸
それでは、学歴以外に評価される実績とは何でしょうか。びーやま氏は、「スポーツや芸術といった分野で圧倒的な成果を出した人は評価される」と述べ、新卒採用においても運動部の出身者が学歴とは別枠で採用されるケースがあることを例に挙げます。しかし、そうした突出した才能を持つ人はごく一部であり、多くの人にとってはその道で成功することは非常に困難です。
この点において、学歴は「超一部の大学学部を除けば、努力だけで埋められる世界」であるという側面が強調されます。つまり、特定の分野での突出した才能がなくとも、個人の努力によって到達しうる指標が学歴であると言えるでしょう。また、スポーツや芸術が競技や分野を跨ぐと評価が難しいのに対し、学歴は文系・理系の差こそあれ、ある程度比較可能な評価軸であるという点も、その重要性の一因として挙げられます。
学生の本分と学歴の関係
さらに、びーやま氏は「勉強は学生の本分である」という視点も提示します。学生時代に「やるべきことをしっかりやってきたか」という問いに対する答えとして、学歴は客観的な指標となり得ます。これは、単なる知識の有無だけでなく、目標設定能力、継続力、問題解決能力といった、社会に出てからも必要とされる基本的な資質を測るものとして機能しているとも解釈できます。
結論
日本の社会において学歴が依然として重視されるのは、特に若年層においては、それが個人の努力と潜在能力、そして将来への期待を測る「分かりやすい実績」として機能するためです。スポーツや芸術分野での突出した才能を持つ一部の人々を除けば、学歴は努力によって獲得可能な、普遍的な評価軸となり得ます。社会に出た後は仕事の実績が重視されるものの、キャリアの初期段階においては学歴がその後の扉を開く重要な鍵となることが少なくありません。