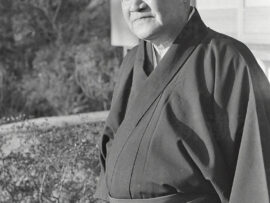「最近の若手は育たない」「なぜ部下が自分で考えて動いてくれないのだろう?」――このような悩みを抱えるリーダーやマネージャーは少なくありません。上司としては、今後の成長を期待し、仕事を任せようと努力するものの、部下の行動量が少なかったり、やる気が見えなかったり、こちらの意図が十分に伝わっていないと感じることもあるでしょう。しかし、部下の成長が停滞している原因は、本当に部下自身の資質にあるのでしょうか。実は、リーダー自身のちょっとした習慣や言動が「誤解」を生み、無意識のうちに部下の成長を妨げているケースも少なくないことが指摘されています。ラーニングエッジ代表の清水康一朗氏は、本来リーダーは部下が自ら考え、挑戦し、失敗から学ぶ機会を創出すべきだと語りますが、現実には逆効果となる場面が多いと警鐘を鳴らしています。
 部下を見守る上司のイメージ。リーダーの行動が部下の成長に大きく影響する。
部下を見守る上司のイメージ。リーダーの行動が部下の成長に大きく影響する。
部下の成長を妨げる上司の「誤解行動」とは
ここでは、部下の自律的な成長や経験の機会を奪いかねない、上司によく見られる3つの「誤解行動」とその具体例を紹介します。リーダー自身の無意識の行動が、部下の思考停止や経験不足を引き起こす原因となっている可能性があります。
1. 会社のルールを自ら破る「悪い前例」
リーダーはチームの模範となるべき存在です。しかし、多忙を理由に会社のルールを軽視したり、私的な解釈で逸脱したりする行動は、部下に対して「結局ルールは守らなくても良い」という誤ったメッセージを与えてしまう恐れがあります。
【事例】
IT企業の営業部に所属する佐藤主任(38歳)は、常に高い成果を出すことに強い自負を持っていました。ある日、「効率が上がる」という理由から、社内規定で禁止されている個人端末でのデータ持ち出しを実行。その様子を目撃した新人の木村さん(24歳)は、「主任が許されるなら自分も良いだろう」と感じ、後に同様の行動を起こしました。結果として情報漏洩のリスクが発覚し、チーム全体が問題に巻き込まれる事態に発展。リーダー自身は「自分なら問題ない」と考えていた行動が、部下にとっては「許される前例」となってしまった典型的なケースです。
2. 部下の「思考停止」を招く過度な介入
部下が自ら考え、解決策を見出すプロセスを尊重せず、上司が先回りして答えを与えたり、過度に介入してすべてを修正したりする行動は、部下の思考力を奪い、主体性を損なわせます。部下は「どうせ上司が最終的に決めるから」と、考えることをやめてしまうかもしれません。
【事例】
企画部門の山田課長は、部下の提出する企画案に対し、細部にわたるまで自ら修正を加え、時には最終的な資料作成まで引き受けていました。「部下のスキルアップのため」という意図でしたが、これにより部下たちは「どうせ課長が直すから」と、深く考え抜くことをやめ、形式的に企画書を作成するだけになってしまいました。結果として、部下たちは自力で課題を分析し、創造的な解決策を導き出す能力が育たなくなっていきました。
3. 挑戦機会を奪い「経験不足」を生む過保護
部下が失敗することを恐れるあまり、上司が困難な業務や責任の重い仕事を経験豊富なベテランにばかり任せ、新入社員には簡単なルーティンワークしか与えないことがあります。これは、部下が新しいスキルを習得し、自信を築く貴重な機会を奪い、結果的に彼らの経験不足を招いてしまいます。
【事例】
製造部門の田中部長は、新人の育成に熱心でしたが、重要なプロジェクトや顧客対応は常に経験豊富な部下Aに一任していました。新人の部下Bには、「まだ早いから」と簡単なデータ入力や資料整理ばかりを指示。これにより、部下Bはいつまで経っても実践的なスキルや問題解決能力を身につける機会を得られず、自信も持てないままでした。田中部長の「部下を守りたい」という気持ちが、結果的に部下の成長機会を奪い、部署全体のスキルアップを阻害する要因となってしまったのです。
まとめ:リーダーが育てるべきは「自ら考える力」
部下の成長は、その資質だけでなく、リーダーの行動や言動に大きく左右されることがこれらの事例から明らかです。上司が無意識のうちに行っている「誤解行動」が、部下の主体性、思考力、そして挑戦する機会を奪い、結果としてチーム全体の生産性や創造性の低下につながる可能性があります。
リーダーは、自身が部下にとっての「模範」であることを常に意識し、自律的な思考と行動を促す環境を整えることが重要です。部下を信頼し、適切な裁量を与え、たとえ失敗してもそこから学べるようサポートすることで、組織全体の持続的な成長と人材育成を実現できるでしょう。
参考文献:
- ラーニングエッジ代表 清水康一朗氏の提言に基づく
- Yahoo!ニュース記事