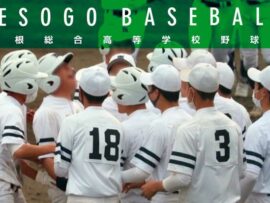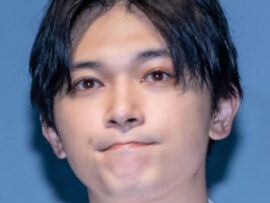秋の行楽シーズンにどこを訪れるべきか、迷う方も多いのではないでしょうか。歴史評論家の香原斗志氏は、単に紅葉の美しさだけでなく、「今だからこそ訪れるべき城がある」と提言しています。本記事では、香原氏が選定した「秋の名城」ランキング2025年版から、特に注目すべき城の魅力をご紹介します。
夏の猛暑を避けて城歩きを楽しむには、秋から春にかけてが最適です。夏は木々が生い茂り、建造物や石垣、土塁が見えにくいことも少なくありません。しかし、秋は涼しく、色づいた木々に囲まれた城は普段とは異なる表情を見せ、格別の美しさを醸し出します。そこで、今回は紅葉の名所でもあり、話題の6城の中から特に彦根城と白河小峰城の魅力に迫ります。
 日本の秋を彩る歴史的な城郭
日本の秋を彩る歴史的な城郭
惜しくも世界遺産推薦見送りとなった彦根城(滋賀県彦根市)
ランキング第6位に選ばれたのは、今年8月26日に開催された国の文化審議会で、2027年の世界文化遺産候補への推薦が惜しくも見送られてしまった彦根城です。彦根城は、徳川四天王の一人である井伊直政を藩祖とする譜代大名筆頭、井伊家の居城として知られています。直政の死後、大坂の豊臣包囲網の一環として徳川家康の支援のもと築城が始まり、慶長20年(1615年)の大坂夏の陣で豊臣氏が滅亡した後は、井伊家単独で工事が進められ完成しました。
国宝に指定されている天守をはじめ、天秤櫓など5棟の重要文化財建造物が現存しています。城の中心部である金亀山の北側には、井伊家の下屋敷に付随して造られた池泉回遊式庭園の玄宮園があり、秋には鮮やかに木々が色づきます。国の名勝にも指定されているこの庭園から望む天守は、彦根城を代表する景観であり、特に紅葉の季節はその美しさを際立たせます。金亀山自体も赤や黄色に染まり、訪れる人々を魅了します。
彦根城が世界文化遺産候補の選から漏れた理由としては、「大名統治システムを有形遺産で示す」というアピールの根拠が弱い点が挙げられました。確かに、そのシステムの一部は残っているものの、「大名統治システム」は幕藩体制下の多くの城に当てはまり、彦根城独自の特性として示すには乏しいとの指摘です。しかし、彦根城には天守、天秤櫓、太鼓門と続櫓など、他城から移築された建造物が数多く残っています。これは日本伝統の木造軸組工法だからこそ可能だった解体と移築の事例であり、欧米の石造建築ではほぼ不可能なことです。彦根城に多くの移築建築が見られるのは、豊臣包囲網の構築を急ぐ必要があったためと考えられますが、この日本独自の建築技術と歴史的背景を強調すべきだったという意見もあります。紅葉の時期には、これらの歴史的建造物と色とりどりの木々を共に愛でることができます。
今こそ訪れたい松平定信ゆかりの城、白河小峰城(福島県白河市)
第5位にランクインしたのは、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」でも松平定信が印象的に描かれた白河小峰城です。この城は東北地方では珍しい総石垣造りの城郭であり、盛岡城、会津若松城と並び「東北の三名城」の一つと称されています。寛永4年(1627年)、10万石の城主として棚倉から白河に移封された丹羽長重(織田信長の家臣だった丹羽長秀の長男)が、幕府の命令により既存の城を大規模に改修し、その姿は幕末までほぼ維持されました。
この改修時に本丸北東隅に建てられたのが、実質的な天守である三重櫓です。戊辰戦争で焼失したものの、平成3年(1991年)に木造の伝統工法を用いて忠実に復元されました。復元された三重櫓と、鮮やかに色づいた紅葉とのコントラストは実に見事な景観を生み出しています。
老中失脚後も松平定信は藩政に専念し、文化9年(1812年)に家督を長男の宗永に譲ってからも藩政の実権を握り続けました。その際、大沼と呼ばれた湿地帯に堤を築き、水を貯めて造成したのが、国の史跡および名勝に指定され、日本最古の公園ともいわれる南湖公園です。白河を訪れた際には、この南湖公園の紅葉も併せて楽しむことをお勧めします。
この秋は、歴史の舞台となった名城で、日本の美しい紅葉を心ゆくまで堪能してみてはいかがでしょうか。