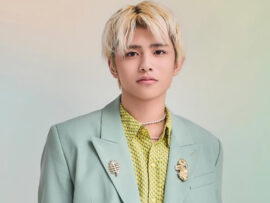東京地裁立川支部で17日、介護していた102歳の母親を殺害したとして殺人罪に問われた71歳の女性に対し、懲役3年・保護観察付き執行猶予5年の判決が言い渡されました。この異例の判決は、介護を巡る過酷な環境と「介護疲れ」がいかに深刻な問題であるかを浮き彫りにしています。女性は「助けてくれる人が思い浮かばず、ひとりぼっちになったような気持ちでした」と証言しており、裁判長も「介護疲れによる事案で、同情の余地が大きい」と述べました。超高齢化社会の日本において、最悪の場合、殺人事件に発展することもある「老老介護」の現場では、一体何が起きているのでしょうか。
日本各地に存在する「老老介護」の現場では、多くの家族が極限状態に追い詰められています。京都府に住む山中光代さん(仮名、60代)も、その一人です。約5年前から、90歳近い母親の介護を一人で担ってきた山中さんは、今回の裁判の判決を聞き、「お母さんを手にかけた女性の気持ち、分かりますよ。私もギリギリの精神状態です」と深く共感の念を示しました。
 老老介護で追い詰められている家族は日本中にいる
老老介護で追い詰められている家族は日本中にいる
認知症による暴言・暴力との闘い
山中さんの母親に異変が現れ始めたのは5年ほど前でした。鍋を火にかけっぱなしにして焦がすなど、物忘れがひどくなったにもかかわらず、本人は認知症の疑いを認めようとしませんでした。山中さんが介護の相談をしようとケアマネジャーを呼んでも、「帰れ!」と玄関先で追い返してしまう状況でした。
しかし、山中さんを最も苦しめたのは、母親の日に日に増す暴言と暴力でした。母親は山中さんの顔を見るたびに「死ね」と口にするようになり、ある日、庭で草刈りをしていた母親に鎌で足を切りつけられるという衝撃的な出来事も経験しました。「痛い! 何すんのお母ちゃん!」と叫んだ山中さんに対し、母親は見たことのないような恐ろしい目つきで睨みつけたといいます。さらに、「お前なんか殺してやる」と包丁を振り回され、腕を切られて警察沙汰になったこともありました。ようやく病院に連れて行くと、母親はアルツハイマー型認知症と診断されました。
介護の現実:身体的・精神的孤立の深化
認知症が進行した現在、母親は足腰が衰え、離れにある自室からほとんど出られない状態です。紙オムツに用を足すと、不快感からか脱いで部屋の中に放り投げることも頻繁にあります。山中さんが汚物を処理しても、母親からは感謝の言葉一つなく、「あんた身内でしょ」という冷たい言葉が返ってくるといいます。「もうキレそうになりますよ。母に愛情なんてありません」と山中さんは語り、精神的な限界を明かしました。
山中さんは障がい者施設で働いており、夜間勤務もあります。仕事を終え、疲労困憊の体で帰宅すると、休む間もなく母親の介護が待っています。その結果、疲労とストレスが限界に達し、職場で倒れてしまったことも一度や二度ではありません。周囲には気にかけてくれる親戚や友人、近隣住民もいますが、山中さんは「田舎あるあるですが、『娘なんだからお母さんのことを看てあげてね』と、周囲からものすごい圧がかかるんです。これを振り切って逃げたら、帰る場所がなくなるという恐怖がある。夜勤明けでも、『私の昼寝中に母に万一のことがあったらご近所から何を言われるか……』と考えてしまい、ろくに眠れません。精神的には完全に孤立しています」と、外からは見えにくい精神的な孤立感を訴えました。
施設入所の壁と地域格差
介護施設を頼ろうにも、現実は非常に厳しいものです。長期的な入居が可能な特別養護老人ホーム(特養)は常に高い倍率で、入居まで何年も待つケースがざらにあります。さらに、入居の条件は原則として要介護3以上の認定を受けていることで、要介護2の山中さんの母親は入所の見込みがほとんどありません。
「別の地域に住む友人は『こっちでは認知症が進行していれば簡単に要介護3の認定が出るよ』と話していて、自治体間の格差に愕然(がくぜん)としました」と山中さんは語り、介護認定における地域間の不公平感に大きな不満を抱いています。中には、特養への入所を早めるために、精神科病院に入院させるという残酷な選択をする人もいると聞きます。入院によって寝たきりの生活を送ることで、体の衰えが進み、要介護度を上げてもらいやすくなるという現実があるからです。
介護現場からのSOS:社会全体での支援が急務
今回の介護殺人における執行猶予判決は、「老老介護」の現場が抱える深刻な問題と、介護者の精神的・身体的負担の限界を社会全体に突きつけるものです。介護疲れによる孤立、認知症による家族への暴力、そして不足する介護インフラと地域格差は、多くの家族を絶望の淵に追いやりかねません。
このような悲劇を繰り返さないためには、介護サービスの拡充、地域における相談支援体制の強化、そして介護者への精神的サポートが不可欠です。個々の家族にのみ介護の重圧を押し付けるのではなく、社会全体で支え合う仕組みを構築し、介護者が孤立しない環境を早急に整備することが求められています。