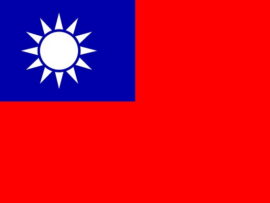今年は原爆投下と終戦から80年という節目の年を迎えます。しかし、世界ではロシアとウクライナの戦争、ガザ地区での紛争が続き、核戦争の可能性も拭えない不穏な情勢にあります。このような時代背景の中、被爆体験を描いた漫画『はだしのゲン』は、多くの人々に原爆の恐ろしさを伝えてきました。ところが近年、この貴重な作品が日本の教育現場から姿を消しつつあるという現状があります。この状況に対し、『はだしのゲン』の作者、故・中沢啓治さんの妻である中沢ミサヨさん(82)は、どのような心境を抱いているのでしょうか。夫の苦悩、当時の被爆者差別、そして『はだしのゲン』誕生にまつわる秘話について、誰よりも近くで啓治さんを支え見守ってきたミサヨさんが語ります。
凄惨な描写への葛藤と夫の信念
ミサヨさんは、夫が描く『はだしのゲン』の凄惨な描写について、かつて「やけどで皮膚がケロイドになったり、身体にウジ虫がたくさん湧いたりする描写は、子どもたちが怖がって読まなくなるから、少し抑えたらどうか」と尋ねたことがありました。しかし啓治さんは、「何を言っているんだ。これでもまだ抑えているんだ。これくらい描かなかったら、原爆の恐ろしさがわからない」と、怒りを込めて答えたといいます。啓治さんは6歳の時に広島で被爆し、父と姉、弟を原爆で亡くしました。彼の作品に込められた強いメッセージは、自らの被爆体験に基づいていたのです。
しかし、創作活動の初期、啓治さんは自身が被爆者であることを公言せず、娯楽漫画を手がけていました。その背景には、当時の社会に根強く存在した被爆者への差別がありました。中沢ミサヨさんは、「被爆者に対する差別が非常に大きかったため、夫はなるべく被爆者だとは言わないように、原爆の話を避けていました」と当時を振り返ります。
 中沢ミサヨ氏、『はだしのゲン』作者・中沢啓治氏を支えた妻の肖像、被爆者差別の時代を生き抜いた証言
中沢ミサヨ氏、『はだしのゲン』作者・中沢啓治氏を支えた妻の肖像、被爆者差別の時代を生き抜いた証言
原爆漫画誕生の原点:母の死と遺骨がもたらした衝撃
中沢ミサヨさんが啓治さんと結婚したのは、終戦から20年余り経った1966年のことでした。その年、啓治さんの最愛の母が亡くなります。ミサヨさんは夫とともに広島での葬儀に参列しました。火葬された母の遺骨はボロボロで、頭蓋骨さえ残っておらず、すべて灰になっていました。この光景を目の当たりにし、啓治さんの心には原爆に対する新たな怒りが沸き上がったといいます。
広島から東京の自宅に戻る間、啓治さんは一言も発することなく、深く沈黙していました。ミサヨさんも夫の苦しみを察し、何も言わずに寄り添いました。葬儀からおよそ2週間後、啓治さんから「原稿ができたから読んでみてくれ」と手渡されたのが、彼の初の原爆漫画となる短編『黒い雨にうたれて』でした。
しかし、この作品を編集部に持ち込むと、「作品は素晴らしいが、テーマが……」と、掲載には慎重な反応が返ってきました。別の編集部でも同様の反応を受け、掲載が決まるまでにはそれから1年を要しました。最終的に掲載が決まったのは、『漫画パンチ』という雑誌でした。啓治さんは編集長から「すごくいい作品だから、ぜひやらせてください。何かあったら一緒に責任を取りましょう」と熱心に言われたとミサヨさんに語ったそうです。『黒い雨にうたれて』は大きな反響を呼び、『黒い川の流れに』『黒い鳩の群れに』と続く「黒い」シリーズへと発展。啓治さんは原爆をテーマにした短編を次々と発表し、1972年には漫画雑誌の企画で自伝漫画『おれは見た』を完成させました。ミサヨさんは、見よう見まねで啓治さんのアシスタントを務め、夫のいちばんの理解者であり、最初の読者として常に支え続けました。彼女自身が夫の被爆体験の全容を知ったのは、自伝漫画を描く現場でのことでした。爆心地から1.3キロという至近距離での被爆体験は、ミサヨさんの想像をはるかに超えるもので、「何もない焼け野原で生き抜くことがどれほど大変だったか。まだ6歳の子どもがよく助かったなと思いましたね」と当時の衝撃を語っています。
長編連載への決断:次世代へのメッセージと差別との闘い
ある日、啓治さんのもとに自身の原爆体験をベースにした長編連載のオファーが届きます。しかし、当時はいまだ被爆者に対する根強い差別が残っていました。「被爆者と接すると病気がうつる」といった根拠のない噂が広まり、社会全体に蔓延していたのです。単発の読み切り企画とは異なり、長期連載となると、彼の被爆体験が世に広く知られることになります。
ミサヨさんは、長編連載の話を聞いて「もう不安で不安で仕方がなかった」と当時を振り返ります。お子さんの将来、結婚など、さまざまな心配が頭をよぎりました。実際に、生命保険の勧誘員から「中沢さんは被爆しているので、お子さんも病気になる確率が高い」と言われた経験もあったといいます。「皆、口に出さずともそう思っているんです」と、当時の社会の偏見を肌で感じていたミサヨさん。
しかし、啓治さんの意思は固く、すでに覚悟を決めていました。彼はミサヨさんに「知らないから差別があるんだ。だから子どもたちにわかるように教えなきゃいけない。次世代の子どもたちに知らせなければいけない。俺は今描かなくちゃいけない。記憶が残ってるうちに描かなければいけないんだ」と強く語ったといいます。「今しかない」という強い思いが彼を突き動かしていたのです。
1973年、『週刊少年ジャンプ』での連載がスタートしました。少年誌での連載は、啓治さんのかねてからの望みであり、子どもたちに原爆のむごさを伝えたいという彼の願いが、この時ついに叶えられたのです。
結び
中沢ミサヨ氏の証言は、『はだしのゲン』が単なる漫画ではなく、中沢啓治氏自身の血と汗、そして被爆者としての葛藤と使命感から生まれた、生きた記録であることを改めて教えてくれます。当時の社会に根強く残った被爆者差別と闘いながらも、「次世代に原爆の真実を伝えたい」という啓治氏の強い意志が、ミサヨさんの支えと共に『はだしのゲン』という不朽の名作を生み出しました。
終戦から80年を迎える今、世界情勢は混迷を極め、核の脅威が再び現実味を帯びています。教育現場から『はだしのゲン』が消えつつある現状は、私たちが歴史から学び、平和への意識を次世代に継承していくことの重要性を再認識させます。中沢夫妻が命懸けで伝えようとした原爆の悲劇と、そこから学ぶべき教訓を、私たちは決して忘れてはなりません。
参考資料
https://news.yahoo.co.jp/articles/b3f3571628238f863dd17b8991a1498ee6eb94a9