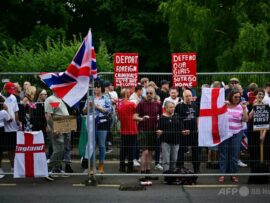食産業のグローバル化が急速に進む中、日本の食産業はどのような戦略をとるべきか。フードテック事業に携わる専門家は、世界で注目されている日本の伝統食文化が、英語での発信力不足により十分にアピールできていない現状を指摘する。本稿では、日本の食産業が現状を打破し、世界市場で存在感を示すための可能性と課題を探る。
これまで日本では、一般消費者による大きなムーブメントや、国が主導する強力な産業政策が食分野で生まれにくい傾向があった。かつての「日の丸半導体」のような国主導の成功例とは異なり、近年の政府の動きは遅く、世界的な潮流から取り残されているという声もある。今後は、産業界が起点となり、生活者のニーズを汲み取りつつ、あるべき産業の姿を提示し、それが国家政策へと繋がるようなアプローチが求められているのではないか。特に、日本の食産業がより多様なグローバル化を実現する可能性に注目が集まっている。
レストランで調理された食事、デパ地下で売られている惣菜、ターミナル駅で人気の駅弁など、これらが美味しさを保ったまま海外へ輸出できるとしたらどうだろうか。実は、最先端の冷凍技術を活用することで、これまで輸出が難しかったデリカ品(調理済み食品)の海外展開が可能になりつつある。
鮮度保持技術「ZEROCO」は、あらゆる食材や食品の美味しさを損なうことなく保存できる技術だ。加工や瞬間冷凍とは異なる手法で、日本のシェフが作った惣菜に保存料などの添加物を使わず長期保存したり、冷凍して輸送したりすることが可能になる。これにより、レストランやスーパーのデリカ品を海外へ輸出できる可能性が生まれる。
 グローバル化する食産業のイメージ
グローバル化する食産業のイメージ
アメリカのホールフーズ・マーケットが発表する「10大トレンド」では、日本の食材(そば粉、ゆずなど)が頻繁に挙げられており、世界的に日本の食材への需要が高まっていることが伺える。こうした需要を取り込むためには、日本企業が個別に売り込むだけでなく、日本国内に業界横断的な「フードテクノロジーセンター」のような開発支援機関を設立することが有効だろう。世界から技術を学びに来てもらう、あるいは日本から組織的に大規模な世界展開を図ることも考えられる。
センターで開発された次世代食品の技術にライセンスフィーを組み込むことで、世界中で売れるほど日本に利益が還元される構造を作る可能性もある。製品輸出だけでなく、ライセンス供与という形での海外展開も重要な戦略となる。
日本発のグローバルムーブメントとして「和食」は世界に広く知られているが、現状は個々のレストランや食品メーカーがそれぞれ孤立して戦っている印象が強い。さらに、英語での発信力が弱いために、日本が得意とする分野が世界の潮流から取り残されるケースも見られる。その代表例が「発酵」だ。
サンジェイインターナショナル(San-J)の佐藤隆氏によると、米国の書店では発酵関連の本が多く並び、一般の人々の関心も高い。ハーバード大学やスタンフォード大学のような名門大学でも発酵に関する講座が設けられ、コーネル大学が2024年に行った「フードハッカソン」のテーマが発酵だったことからも、その注目度の高さがわかる。
しかし、そこで「日本の発酵文化」が語られることは少ないのが現状だ。フードテックエバンジェリストの外村仁氏は、「発酵食品が豊富で、発酵に関する書籍も多い日本から、英語での情報はほとんど発信されていない」と問題点を指摘する。アジアの発酵食品として世界で連想されやすいのは、残念ながら韓国のキムチ、というのが現実である。

日本の食産業が世界市場で真に存在感を示すには、最先端技術の活用による新たな輸出形態(惣菜など)の開拓に加え、世界に誇るべき伝統文化、特に発酵文化の魅力を戦略的に、かつ英語で積極的に発信していくことが不可欠だろう。技術と文化の両輪で、日本の食のポテンシャルを最大限に引き出す戦略が求められている。
【参考文献】
田中宏隆・岡田亜希子『フードテックで変わる食の未来』(PHP新書)