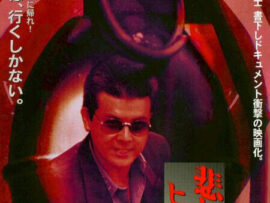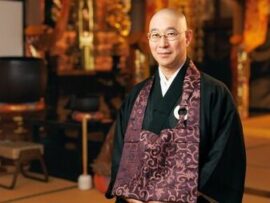外食産業全体が様々な逆風に直面する中、回転寿司チェーンも例外なく、コメ価格の高騰、人件費、水道光熱費の増加といった負担増に直面しています。こうした厳しい状況下でありながら、他の競合を抑え大幅な増収増益を達成しているのが、国内最大手の「スシロー」です。その成功の背景には何があるのでしょうか。スシローの好調ぶりから、回転寿司業界の現状と消費者意識の変化が見えてきます。
逆風下での業績差とその要因
くら寿司が2025年10月期上期に営業利益でおよそ5割の減少を記録し、「かっぱ寿司」を運営するカッパ・クリエイトも2025年3月期に15.3%の営業減益となるなど、多くの回転寿司チェーンが苦戦を強いられています。一方で、「スシロー」を運営するFOOD&LIFE COMPANIESの2025年9月期上期決算では、営業利益がおよそ6割増と顕著な業績拡大を達成しました。
この業績の差はどこから生まれたのでしょうか。興味深いことに、これら3社はいずれも原価率が前年とほとんど変わっていません。これは、原材料費の高騰分を価格に転嫁していることを意味します。つまり、価格設定だけが業績を左右する決定的な要因ではないということです。業績に違いが出た主要因は「集客力」にあると考えられます。価格転嫁によって客数が減少すれば売上は伸び悩み、固定費が収益を圧迫します。逆に、「スシロー」のように客数を維持または増加させることができれば、増益へと繋がります。
具体的な数字を見てみましょう。2025年1月から6月までの期間で、客単価は「スシロー」が前年比6.2%上昇、「かっぱ寿司」が7.5%上昇、「くら寿司」が3.1%上昇しました。価格転嫁は各社で行われています。しかし、客数では大きな違いが出ました。「スシロー」は5.5%増加したのに対し、「かっぱ寿司」は10.2%減少、くら寿司は4.7%減少しています。結果として、「スシロー」の売上高は客単価増と客数増の相乗効果で12.0%も増加しました。対照的に、「かっぱ寿司」は3.4%減、くら寿司は1.7%減となりました。「スシロー」は、まさに回転寿司業界において圧倒的な集客力を誇る一強と言える状況です。
 スシローの店舗外観:逆風下の回転寿司業界で好調を維持
スシローの店舗外観:逆風下の回転寿司業界で好調を維持
消費者意識の微妙な変化が影響?
各社とも低価格を売りにし、原価率も40%台で大きな乖離がないことから、提供される寿司の鮮度や美味しさ、サービス力には理論上大きな差はないと考えられます。それにも関わらず、これほどの集客力の差が開いた背景には、消費者意識の変化があるのかもしれません。
マルハニチロが毎年実施している「回転寿司に関する消費者実態調査」は、この点を示唆しています。この調査は、全国の15歳から59歳までの男女で、月に1回以上回転寿司店を利用する層を対象としています。コロナ禍を経てインフレが進む中で、消費者の重視する点に興味深い変化が見られます。
「回転寿司店を選ぶ際に重視している点」という質問への回答では、「値段が安い」が長年にわたりトップを維持しており、これは変わりません。続いて多かったのは「ネタが新鮮」、「ネタの種類が豊富」でした。重要なのは、これら「鮮度」と「種類」に関する回答割合の変化です。2019年調査では「ネタが新鮮」が41.2%でしたが、2025年には27.0%まで低下しました。同様に、「ネタの種類が豊富」も33.9%から25.0%に減少しています。寿司の味覚に直結すると思われがちなこれらの要素の重要度が、大きく低下したのです。
一方で、「家から近い」という回答が注目すべき変化を見せています。2019年調査では7番目だったのが、2025年には4番目に浮上しました。そして、2025年の回答比率は24.2%となり、「ネタの種類が豊富」とほとんど変わらない水準にまで上昇しています。これは、消費者にとって「近さ」が店舗選びにおいて以前よりはるかに重要な要素となっていることを示唆しています。
まとめ
これらの調査結果から、今日の消費者は、ある一定レベルの品質を提供する回転寿司チェーンであれば、「より近所にある店」、あるいは「身近に感じられ、ブランド認知度の高い店」を選ぶ傾向が強まっている可能性が考えられます。コメ価格や諸経費の高騰による価格上昇が避けられない状況下で、単に「安い」「ネタが新鮮」といった従来の強みだけでは、集客を維持するのが難しくなっています。「スシロー」の圧倒的な集客力は、価格転嫁をしつつも、この変化した消費者意識、特に「近さ」やそれに伴う利用のしやすさといった利便性へのニーズを捉えることに成功している結果と言えるでしょう。
参考資料